-2-1024x538.jpg)
建設業許可を取得するにあたって「経営業務管理責任者の要件」ほど、重要なものはありません。建設業許可を取得するための他の要件は満たしているにも関わらず、経営業務管理責任者の要件を満たしていないがために、許可取得をあきらめなければならないというケースは非常に多いです。
そこで、このページでは、経営業務管理責任者の要件について説明するとともに、要件を充足していることを証明するための資料についても解説していきたいと思います。
なお、令和2年10月の建設業法改正で「経営業務管理責任者」に関する基準の見直しがおこなわれ「常勤役員等」という表記に変わりました。しかし、実務上は、経営業務管理責任者(略して「経管」)という表現が広く使われていますので、ここでも「経営業務管理責任者」もしくは「経管」という記載で統一したいと思います。
- (ア)申請会社の常勤の取締役であること
- (イ)5年以上の取締役または個人事業主としての経験があること
- (ウ)上記の期間、建設業をおこなっていたこと
「経営業務管理責任者」という言葉をはじめて聞く人もいるかもしれません。「建設業許可を取得するには経管が重要だ」といったところで、経管の中身を理解できていなければ、その重要性の認識もままなりません。そこで、まずは、経管の中身について、説明をしていきたいと思います。
(ア)申請会社の常勤取締役
建設業許可を取得するには、許可を取得する会社の「常勤取締役」の中に、経管がいなければなりません。一部、例外的に「常勤執行役員」でも許可を取得することができますが、あくまでも例外措置なので、ここでは「常勤の取締役」と覚えておいてください。
(イ)5年以上の取締役または個人事業主の経験
経管の要件を充足するには
- 取締役としての経験が5年以上
- 個人事業主としての経験が5年以上
- 取締役+個人事業主としての経験が5年以上
のいずれかが、なければなりません。この点についても、一部、例外的に取締役、個人事業主の経験ではなく、執行役員や部長の経験が5年以上あれば経管の要件を満たすという考え方もありますが、ここでは、上記の3つのパターンに絞られると覚えておいてください。
(ウ)建設業をおこなっていたこと
さらに経管の要件を充足するには、建設業をおこなっていた会社の取締役としての経験が5年以上、建設業をおこなっていた個人事業主としての経験が5年以上といったように、取締役および個人事業主であった期間は、いずれも建設業の経営に関するものでなければなりません。この点についても、一部例外がありますが、例外事由が極めて狭く、その例外事由に該当することを証明するのが、極めて困難であることから、例外事由については、ここでは省略します。
たとえば、某建設会社の取締役に5年間就任していたという人は、経管の要件を満たします。また、個人事業主として建設業を5年間以上おこなってきたという人も、経管の要件を満たします。さらに、個人事業主として3年、法人成りして代表取締役として2年間、建設業をおこなってきたという人も経管の要件を満たします。
一方で「建設会社の取締役に就任したことがあっても2年間だけという人」や「サラリーマンとして勤めあげてきた会社を退職し、1人親方として独立後、個人事業主として3年しかたっていないという人」も、残念ながら経管の要件を満たすことができません。
建設業許可を取得する際の重要な要件である経管の中身について、おおよその理解はできたでしょうか?「建設会社での取締役の経験」や「建設業を営んでいた個人事業主としての経験」など、通常の一般人にとっては少しレアな経験が必要なことがお分かりいただけたかと思います。それでは、続いて、上記の要件をどのように証明していけば良いのか?について説明をしていきたいと思います。
(ア)申請会社の常勤の取締役であることの証明
まず、経管は申請会社(=これから建設業許可を取得するために申請する会社)の「常勤」の「取締役」であることが必要です。この(ア)の要件を証明するための証明方法を見ていきます。
申請会社に「常勤」しているか否かについては、通常は健康保険証で確認することが可能です。1人の人が2枚の健康保険証をもつことができないことになっているので、健康保険証の記載(事業所名称)を確認すれば、申請会社に常勤しているか否かがわかります。申請会社の「取締役」であるか否かについては、会社の登記簿謄本で証明します。会社の登記簿謄本は手数料を払うことによって、法務局で簡単に取得できますので、それほど、難しくはありません。
(例:A建設会社が、取締役のXさんを経管にして、建設業許可を取得する場合)
XさんがA社の取締役であることは、登記簿謄本によって証明します。また、Xさんは、A社という会社名の記載が入った健康保険証を持っていなければなりません。もし仮にXさんが、B社という会社の健康保険証を持っていたら、Xさんは、A社に常勤しているのではなく、B社に常勤していることになります。この場合、Xさんは、A社の常勤ではないため、Xさんを経管にしてA社が建設業許可を取得することはできません(出向などの一部特殊な場合を除いて)。
また、健康保険組合に加入している会社の場合、そもそも、健康保険証に事業所名の記載がない場合もあります。また、経管が後期高齢者の場合、後期高齢者医療被保険者証にも事業所名の記載がありません。そういった場合には、
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
- 直近決算の法人用確定申告書(役員報酬明細)
- 厚生年金の被保険者記録照会回答票
などによって、経管の常勤性を証明することになります。それぞれ、
- 住民税は給料からきちんと特別徴収されているか?
- 常勤の取締役にふさわしい役員報酬が支払われているか?
- 現時点で申請会社の厚生年金に加入しているか?
といったことが経管の常勤性を判断する材料に使われます。先ほどの例でいうと、経管Xさんが、取締役としてA社に常勤しているということであれば、Xさんに支払う給料から住民税が特別徴収されているはずですし、Xさんには、常勤の取締役としてふさわしい額の役員報酬がA社から支払われているはずです。また、Xさんは、A社の厚生年金に加入しているはずです。上記のような資料によって、申請会社での「常勤」の「取締役」であることを証明します。
(イ)取締役又は個人事業主の経験が5年以上あることの証明
それでは、続いて、(イ)の要件「取締役または個人事業主としての経験が5年以上あること」については、どのように証明していけばよいでしょうか?まず、取締役については、法務局で取得できる登記簿謄本によって、確認することができます。登記簿謄本には取締役の就任日や退任日・辞任日の記載がありますので、その会社に何年間取締役として在籍していたかを確認することができます。なお、履歴事項全部証明書で確認できないような古い経歴については、閉鎖事項全部証明書を取得して確認することになります。
続いて、個人事業主については、税務署に提出している確定申告書の控えで確認することになります。個人事業主である以上、税務署への確定申告は必須です。そのため、税務署へ提出した確定申告の控え(5期分以上)を使って、個人事業主の経験が5年以上あることを証明します。なお、個人事業主が法人成りしたように、個人事業主としての経験と法人の取締役としての経験を合算して5年以上の経験を証明しようとする場合には、個人事業主時代の確定申告書および法人設立後の登記簿謄本の両方が必要になります。
(ウ)その間、建設業をおこなっていたことの証明
それでは、(ウ)の要件「取締役または個人事業主としての5年以上の間、建設業をおこなっていた(経営していた)こと」の証明はどのようにすればよいのでしょうか?この点については「建設業許可を持っている(いた)会社での経験」と「建設業許可を持っていない会社での経験」というように、証明の仕方を2つに分けて考える必要があります。
(建設業許可ありの場合)
「現在も継続して建設業許可を持っている会社」もしくは、「過去一定の期間、建設業許可を持っていた会社」での取締役としての5年以上の経験がある場合。この場合は、建設業の許可証や許可行政庁に提出している申請書・各種変更届の副本で、建設業をおこなっていたことの証明をすることができます。
たとえば、○○年~××年までの過去5年間、A建設株式会社の取締役に就任していたBさんを経管とする場合。登記簿謄本で、「Bさんが、○○年~××年までの間、A建設株式会社の取締役であったこと」を証明するとともに、A建設株式会社の許可通知証や変更届の副本によって、「A建設株式会社が○○年~××年までの5年間、建設業許可を持っていたこと」を証明すればよいわけです。
(建設業許可なしの場合)
建設業許可を持っていない会社の場合。建設業許可を持っていないわけですから、建設業の許可証や許可行政庁へ提出している届出の副本で、建設業をおこなっていたことを証明することができません。その場合には「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」などで、工事の実績(建設業をおこなっていたこと)を証明していくことになります。
たとえば、現時点から遡って、5年以上前から、株式会社C工業の取締役に就任しているDさん。このDさんを経管にして建設業許可を取得しようとする場合。5年以上前から株式会社C工業の取締役に就任していることの証明は、登記簿謄本で行うことができます。5年以上前から株式会社C工業で工事をおこなっていることの証明として、「工事請負契約書」「工事注文書・請書」「工事の請求書・入金記録」を用意することになります。
経管の中身、そして証明方法ついて説明してきましたが、少しややこしく感じている人もいるかもしれません。そこで、知識の整理のためにも、実際に相談が多いパターンを挙げて、経管の要件を充足するか否かについて、説明していきたいと思います。
(株)中村メンテナンスからの相談
 |
主な業務は、給排水設備や空調設備の販売です。最近になって、性能の良い高品質でかつ最先端の機器・設備の販売を手掛けるようになりました。設置工事自体の費用は数十万円程度であるものの、設備の販売代金と合わせると500万円以上の費用がかかるようになってきました。現社長の中村社長は、(株)中村メンテナンスの代表取締役に就任して10年以上たちますが、管工事の建設業許可を取得することは可能でしょうか? |
|---|
まず前提として、仮に設置工事自体に係る費用が500万円未満であったとしても、設備や機器の販売代金と合算して500万円以上になるようであれば、建設業許可を取得しなければなりません。建設業許可取得の基準となる500万円という金額は、機器の販売価格と設置工事の費用を合算して判断するからです。そのため、(株)中村メンテナンスのように、設置工事自体の費用は500万円を下回っていたとしても、設備の販売代金と合わせて500万円以上かかるようであれば、建設業許可取得が必要になります。
経管の要件を証明できるか?
それでは、(株)中村メンテナンスは、中村社長を経管にして建設業許可(管工事)を取得することは可能でしょうか?
(ア)申請会社の常勤取締役であることの証明
まず、中村社長は(株)中村メンテナンスの代表取締役ですから、申請会社である(株)中村メンテナンスに「常勤している取締役」に該当しているといえます。この点については、登記簿謄本のほか、健康保険証や住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)などで証明していくことになります。
(イ)取締役としての経験が5年以上あることの証明
続いて、中村社長は(株)中村メンテナンスの代表取締役に就任して10年以上経過しているので「取締役としての経験が5年以上ある」ということもできます。この点についても、登記簿謄本を取得して確認すれば足ります。
(ウ)その間、建設業をおこなっていたことの証明
それでは「その間、建設業をおこなっていたことの証明」はどうすればよいでしょう?中村社長には、取締役としての経験が5年以上ありますが、取締役として経験を積んだ5年間、(株)中村メンテナンスは建設業許可を取得していない未許可業者です。そのため、建設業の許可証などで建設業を行っていたことの証明をすることができません。
この場合「建設業許可を持っていない会社での経験の証明」ということになり、管工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」を使って、5年以上の間、実際に、管工事をおこなっていたことを証明することになります。
以上の証明に成功すれば、経管の要件を満たしますので、その他(専技)の要件を満たせば、建設業許可を取得することができるということになります。
4.工事実績なし。(株)サトー不動産のケース
(株)サトー不動産からの相談
 |
不動産販売・仲介の業者ですので、建設工事をおこなった実績はありません。しかし、将来的には工事を手掛けることになるかもしれないので、今のうちに(取れるうちに)建設業許可を取得したいと考えています。なお、現社長の佐藤社長は、(有)サトー不動産の代表取締役に就任して5年以上たちます。しかし、(有)サトー不動産に、工事の実績や経験がないので、どのようにして建設業許可を取得すればよいでしょうか? |
|---|
工事の経験や実績がないと、建設業許可を取得できないと勘違いをしている人も多いのですが、実は、申請会社自体に工事の経験や実績がなかったとしても、経管の要件を満たした人を社内に招き入れることによって、建設業許可を取得することは可能です。早速(有)サトー不動産のケースで見ていきましょう。
経管の要件を証明できるか?
佐藤社長が代表を務めている不動産会社なのですから、佐藤社長を経管として建設業許可を取得したいところです。佐藤社長は、(有)サトー不動産の「代表者として会社に常勤(ア)」していますし、「取締役としての経験が5年以上(イ)」あります。しかし、(有)サトー不動産には工事を請負ったり、施工したりした経験がないため、取締役としての5年間、「建設業をおこなっていたことの証明(ウ)」ができません。残念ながら(有)サトー不動産の中には経管の要件を満たしている人はいないということになります。そのため、建設業許可を取得するには、経管や専技の要件を充足している人を外部から招聘し、(有)サトー不動産の常勤取締役に就任させる必要があります。
ここで、佐藤社長から、「学生時代の親友である田中さんが経管の要件を満たしているのではないか?」という相談がありました。田中さんは大手ゼネコンの取締役を経験後、早期退職をして、現在はどこの会社にも所属することなく隠居生活を送っています。この場合、田中さんの経管の要件を証明するにはどうすればよいでしょうか?田中さんの、経管としての要件を証明する方法を見ていきましょう。
(ア)申請会社の常勤取締役であることの証明
まず、田中さんを(有)サトー不動産の「常勤の取締役」として招き入れる必要があります。田中さんの(有)サトー不動産への健康保険への加入そして、取締役就任の登記をすれば、「申請会社の常勤取締役」であることを証明できます。
(イ)取締役としての経験が5年以上あることの証明
続いて、大手ゼネコンで「取締役を5年以上経験していたこと(イ)」の証明は、大手ゼネコンの登記簿謄本を取得すれば証明することができます。
(ウ)その間、建設業をおこなっていたことの証明
さらに「その5年以上の間、建設業をおこなってきたことの証明(ウ)」ですが、大手ゼネコンは、当然ながら「建設業許可を持っている会社」です。そのため、その5年間、建設業をおこなってきたことは、田中さんの元勤務先である大手ゼネコンから、許可証や変更届の副本を入手することによって証明できそうです。以上で、田中さんは、経管の要件を満たしますので、その他(専技など)の要件を満たせば、建設業許可を取得することができるということになります。
 |
法人を設立して半年がたちますが、いまだに建設業許可の取得の仕方がわかりません。友人にも相談しましたが、さっぱりです。個人事業を経て法人化し、夫婦で経営している小さな会社なので、資格者や要件を満たしている人を外部から招き入れたり、建設業許可取得のために新たに人を採用するというのは、考えにくいです。うちのような会社でも経管の要件を証明し、建設業許可を取得することができますか? |
|---|
建設業界において、まずは親方のもとで修業をして一定の期間を経た後、個人事業主として独立するというケースが多いように思います。個人事業主として独立後、さらに経験を積んで、事業拡大に伴い個人事業主を法人化するという手続きは、弊所でも何回もサポートしています。それでは、(株)加藤防水の加藤社長のようなケースでも経管の要件を証明して建設業許可を取得することができるのでしょうか?
経管の要件を証明できるか?
(株)加藤防水は、加藤社長のほか、社長の奥さんがパートで経理をしている会社であるため、(有)サトー不動産のように外部から経験者を採用することは全く考えていません。そのため、建設業許可を取得できるか否かは「加藤社長が経管の要件を満たすか否か」にかかっていると言っても過言ではありません。
(ア)申請会社の常勤取締役であることの証明
まず加藤社長は、(株)加藤防水の代表取締役ですから「申請会社の常勤の取締役」という要件は満たしています。
(イ)取締役としての経験が5年以上あることの証明
続いて「取締役または個人事業主としての5年以上の経験」はどうでしょう?この点については、法人を設立してから半年ということですが、それ以前の個人事業主の経験と法人設立後の代表取締役としての経験が5年以上あれば、問題ありません。個人事業主の経験は税務署に提出している確定申告書の控え、代表取締役としての経験は登記簿謄本で証明可能です。
(ウ)その間、建設業をおこなっていたことの証明
では、「その間、建設業をおこなっていたこと(ウ)」の証明はどうでしょうか?加藤社長の個人事業主時代も、法人成りしたあとの(株)加藤防水にも、建設業許可がありません。そのため、(ウ)の「建設業許可がない場合」に該当します。ということは、個人事業主時代の防水工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」、さらに法人設立以降の防水工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」で工事をおこなっていたことの証明をすることになります。上記資料によって、個人事業主時代の4年半+法人成りしてからの半年間=合計5年間の防水工事の経験を証明できれば、経管の要件を充足し、建設業許可を取得することが可能であると言えます。
過去に経管の経験のある人を執行役員にする場合
 |
過去に他県で建設業許可を取得していた知り合い(Aさん)を、取締役ではなく執行役員として会社に招き入れて、東京都の建設業許可を取得したいです。会社の都合上、どうしてもAさんを取締役にすることができないため、執行役員として経管にするにはどうすればよいですか? |
|---|
これは、過去に経管として認められ、建設業許可を取得したことがある人を、申請会社の執行役員にして建設業許可を取得するパターンです。
- 申請会社の常勤取締役であることの証明(ア)
- 取締役の経験が5年以上あることの証明(イ)
- その間、建設業をおこなっていたことの証明(ウ)
のうち、(ア)の例外パターンであるといえます。なぜなら、Aさんは過去に経管として認められたことがあるのですから、その時点で(イ)と(ウ)については、証明できていたということになるからです。
この件については、執行役員が取締役と同等の権限をもつと認められる資料として、申請会社の「組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」「執行役員規則」などを都庁に提出し、事前審査を経たうえで、建設業許可取得にこぎつけた実績があります。問題になったのはあくまでも申請会社での「執行役員」というポジションであったため、申請会社に関する上記資料の提出だけで済んだのが、許可取得に至った大きな理由です。
前の会社の執行役員の5年の経験を用いる場合
 |
Bさんは、長年、グループ会社(建設業許可あり)の執行役員として、建設業部門を統括していました。この度、弊社で建設業許可を取得するにあたって、Bさんを取締役にして、建設業許可を取得したいのですが、取締役の経験がなく、執行役員としての経験しかないBさんを、経営業務管理責任者にして、建設業許可を取得することはできますか? |
|---|
過去に取締役の経験があったAさんの場合と違って、Bさんは取締役としての経験がなく、執行役員としての経験しかありません。
- 申請会社の常勤取締役であることの証明(ア)
- 取締役の経験が5年以上あることの証明(イ)
- その間、建設業をおこなっていたことの証明(ウ)
の3つの要件を見ていくと、Bさんには、「取締役の経験」ではなく「執行役員の経験」しかないことから(イ)の例外パターンということになります。Bさんは、申請会社の常勤取締役になることを承諾しており、(ア)については問題ありません。また、Bさんが在籍していた会社は、建設業許可を持っている会社ですので(ウ)の「建設業許可を持っている場合」ですので、その会社の許可証などをお借りできれば「その間、建設業をおこなっていたこと」は証明できそうです。
AさんとBさんの違いは、おわかりでしょうか?過去に経管として認められた経験のあるAさんを、申請会社の執行役員として建設業許可を取得しようとするケースと、過去に経管として認められたことがなく、取締役としての経験もないBさんを申請会社の常勤取締役として建設業許可を取得しようとするケースです。Bさんのケースでは、前にいた会社から「会社の組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」「執行役員規則」などを、お借りしなければなりませんでした。これは「形式的には執行役員ではあったものの、取締役と同等の権限で、建設業務にあたっていたこと」を証明するためです。
グループ会社や親子関係にある会社など、前の会社が、「業務分掌規程」や「執行役員規則」の提出に協力的であれば、この場合でもBさんを取締役に招き入れ、経営業務管理責任者として、建設業許可を取得することは可能です。しかし一方で、前の会社が、非協力的であった場合、Bさんの執行役員としての長年の経験を証明することは難しいです。その場合には、建設業許可を取得することができないといってよいと思います。
7.経営業務管理責任者の要件・証明方法でお困りの人へ
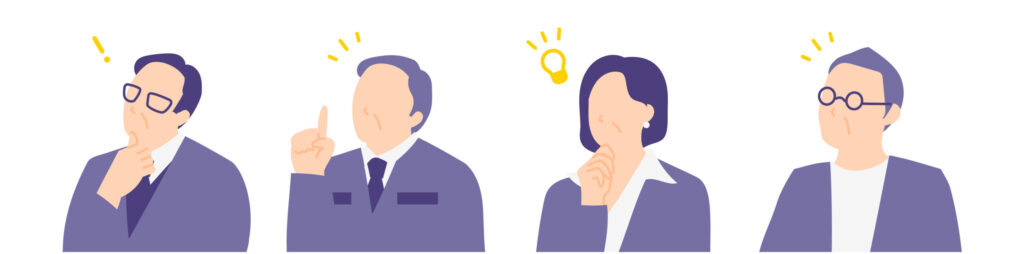
このページの冒頭に記載しましたが、建設業許可を取得するにあたって「経営業務管理責任者の要件」ほど、重要なものはありません。いままで、経営業務管理責任者の要件を証明することができず、泣く泣く建設業許可の取得をあきらめざるを得なかった建設会社をたくさん見てきました。
しかし、まだ諦める必要はありません。
経営業務管理責任者の要件をクリアする方法は、ケースによって異なります。必要な証明書類の収集、役員構成の見直し、グループ会社との関係整理など、解決策はさまざまですが、「正しい知識」と「適切な手続き」さえあれば、許可取得の道は開けます。
行政書士法人スマートサイドは、経営業務管理責任者の要件に関する 豊富な知識と実績 を持つ専門家集団です。過去には、
✅ 要件を満たしていない」と思われたケースを覆し、許可取得に成功
✅ 証明が難しい過去の経営経験を適切に整理し、審査に通過
✅ 依頼者に最適な要件充足の方法を提案し、スムーズに申請完了
といった実績を多数有しています。
「うちの会社では無理かもしれない…」とお考えの経営者様こそ、一度、スマートサイドの有料相談をご活用ください。
- 具体的にどんな証明ができるか
- どうすれば最短で許可を取得できるか
- 他にどんな選択肢があるのか
など、御社の状況を踏まえた最適なアドバイスをお伝えします。建設業許可の取得を諦める前に、まずは専門家に相談を。スマートサイドの有料相談をお申し込みいただき、許可取得への第一歩を踏み出しましょう。

-scaled-e1738530668562-1024x328.jpg)












