<目次>
はじめに いますぐ建設業許可が必要なあなたへ
・いますぐ建設業許可を取得したい…
・どうしても急ぎで建設業許可が欲しい…
私は、いままで何回この言葉を聞いてきたことでしょう。お客様のご希望通り、建設業許可が取得できればよいのですが、かならずしも、すべての会社が許可取得にたどりつけるわけではありません。
ときには、
・こんなに許可取得が難しいなんて制度がおかしい!
・都庁の審査担当者に文句を言いに行ってくる!
と怒り出す社長もいるくらい「いますぐ」「急ぎで」建設業許可を取得することは、難しい作業です。
ですが、なかには「意外とあっさり」許可を取得できてしまう会社もあります。
この違いは何でしょうか?泣く泣く建設業許可の取得をあきらめなければならない方と、短期間で比較的スムーズに建設業許可を取得できてしまう方。
その答えを導き出すために、この文章を記載しているといっても過言ではありません。
この文章は、どうしても急ぎで建設業許可を取得したいという方に向けて書いたものです。「いつか取得できればなぁ~」「3年後に取得できればいいと思っている」という方にとっては、必要ないかもしれません。
しかし、「いますぐ」「急ぎで」建設業許可を取得したいという方は、ぜひ、あきらめずに、最後までお読みください。きっと、あなたが建設業許可を取得するヒントがあるはずです。
第1章_1週間以内に建設業許可が必要なとき、何から始めればいいか?

このページをご覧になっているみなさんは、ほとんどが、はじめて建設業許可の取得にチャレンジする方だと思います。
あたりまえですね。「申請手続きを熟知した人」は、読む必要がありませんし、何回も申請手続を経験している「行政書士」に向けて書いたページでもありません。
そのため、まずは、はじめて建設業許可の取得にチャレンジする方が、建設業許可取得に向けて何からはじめればいいか?という基本から説明をはじめていきたいと思います。
1.いますぐ建設業許可が必要なときとは、どんなとき?
(1)元請・取引先からの圧力
みなさんの中には、元請会社や取引先から「そろそろ建設業許可を取得して欲しい」とか、「建設業許可がないと、これから先、工事を発注することができない」といった許可取得の催促・要請を受けたことがある方は、いらっしゃいませんか?
ときには「いますぐ建設業許可取得に向けて、何とかしろ!」と、強引に許可取得に向けたアクションを迫られるケースもあるようです。
実は、ここ数年、「元請会社や取引先から、建設業許可の取得を催促されて、どうしても急ぎで建設業許可を取らなければならない」と切羽詰まった状態で、私の事務所に相談に来られる社長が急増しています。
建設業許可を持っていないという理由で、仕事が減ったり、売上が減ったりしたのでは、たまったものではありませんね。従業員に給料を払わなければならないし、ボーナスを期待している社員だっている。会社の存続のために自分の役員報酬をぎりぎりまで減らしている経営者も少なくないと思いますが、これ以上、売上や仕事が減ったら死活問題になりかねません。
「今までは、何にも言われなかったのに!」とか、「許可が必要になるような大きい工事はやっていない!」と、許可取得を催促されたことに対する不満もあると思います。
一方で、「いずれ許可を取らなければならないと思っていたので、この機会に建設業許可取得にチャレンジしてみたい」とか「付き合いの長い取引先からの要望だから、その期待に応えられるように何とか許可を取得したい」といったような前向きな意見が聞かれるのも事実です。
みなさんの周りを見渡してみると、実際に、建設業許可を取得して大きな工事を受注し売上を伸ばしている仕事仲間もいるはずです。「自分にだってやればできる」という思いがこみ上げてきませんか?
(2)コンプライアンス意識の高まり
建設業許可を持っていないと500万円以上の工事を施工することができません。許可を持っていないのに500万円以上の工事を施工することは、建設業法違反になります。「500万円以上にならないように請求書を分割して発行してもらっている」という話も聞いたことがありますが、やはりこれも建設業法違反に変わりありません。
私の長年の経験から推測するに、建設業許可の取得を催促する元請会社や取引先は、上記のようなグレーな扱いをせずに、「クリーンで法律違反のない経営をしたい」との思いから、みなさんの会社にも建設業許可取得を促しているように思います。
「そんなこと言われたって…」と、まだ納得いかない方は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」(https://www.mlit.go.jp/nega-inf/)を確認してみるとよいでしょう。みなさんの会社や取引先が、法律違反を理由に行政処分を受けると、国土交通省のWEBサイトで過去の行政処分歴等を公表されることになりかねません。
法令違反というのは、それほど、怖いものなのです。
2.現実的に、1週間以内の建設業許可取得は可能なのか?
元請会社や取引先からの建設業許可取得の要請が、「法令遵守やコンプライアンス意識の高まり」といった「社会の流れ」からくるものだとしたら、みなさんも積極的に応じていきたいですね。
「うちの会社には、建設業許可なんて必要ない!」と言っている場合ではないようです。
(1)1週間以内の許可『取得』
では、このページのタイトルにあるように現実的に、1週間以内の建設業許可取得は可能なのでしょうか?
みなさんは、どう思いますか?少しの時間、考えてみてください!
・気合を入れて、徹夜で準備すれば、余裕でしょ!
・事務員に全部やらせるから、1週間あれば、十分!
・いやいや、建設業許可の取得は、そんなに簡単ではないはず!
・同業が「建設業許可取得には、相当苦労した」と嘆いていた!
どうですか?1週間以内の建設業許可取得は、できそうですか?
実は、建設業許可を取得するまでの期間については、からくりがあります。結論から言うと、1週間での建設業許可の『取得』は、不可能です。
なぜかというと、みなさんが一生懸命に頑張って、どんなに早く書類を準備して申請をしたとしても、申請してから許可が下りるまでの「審査」に、1か月程度の時間がかかってしまうからです。こればかりは役所の都合なので、どうしようもありません。
都庁や県庁の建設業課に申請書類を持参して、建設業許可を申請したとしても、その場で、許可が下りるわけではありません。「書類の不足がないか?」や「許可要件を満たしているか?」の大まかなチェックが行われ、明らかな不備がなければ、持参した副本に受付印を押してもらうことはできます。しかし、許可が下りて、晴れて建設業許可業者になるには、さらに細かい審査を経なければなりません。許可通知書が、みなさんのもとに届くまでには、申請からひと月程度、時間がかかります。
「申請から、およそひと月後に許可通知書を取得できる」という流れになるわけです。
ということは、どんなに「根性や気合」で準備しても、それこそ「徹夜で寝ないで申請書類を書き上げた」としても、1週間以内に建設業許可の『取得』をすることはできません。
とはいうものの、ここであきらめないでください。
(2)1週間以内の許可『申請』
1週間以内の建設業許可の『取得』が無理だったとしても、1週間以内の建設業許可の『申請』ならばどうでしょう?詳しくは「第2章 建設許可をスピード取得するためのテクニック」で説明しますが、1週間以内の『申請』ならば、可能であるというのが私の持論です。
先ほど説明した通り『申請』の際には、大まかなチェックが行われ、持参した申請書の副本に受付印を押印してもらうことができます。この受付印は、都庁や県庁の建設業課が「許可申請を受け付けた」という証拠になるものです。ということは、現実的には、1週間以内の許可の『取得』ができなかったとしても、1週間以内の許可の『申請』を行うことによって、元請会社や取引先に「受付印が押印された申請書類の副本」を提示することができるわけです。
「建設業許可を取得してください」といった要望に対して、真摯に対応しているという姿勢を示すことができます。
これだけでも、元請会社や取引会社に対する信頼につながると考えることができそうです。
3.必要な許可要件を、正しく理解しよう!
それでは、1週間以内の建設業許可の申請を行うには、何からはじめればよいのでしょうか?「何からはじめるか?」というのは、とても大事な視点です。みなさんの中には「何から始めればよいのかわからない」といった人も少なくないと思います。
「何からはじめるか?」と聞かれれば、迷うことなく「許可要件を正しく理解する」ということ以外にありません。
みなさんもご存知かと思いますが、建設業許可は欲しいからといって、取得できるものではありません。法律に定められた「要件」を満たして、はじめて建設業許可を取得できるといった建前になっています。そのため、「許可要件を正しく理解する」ということが何よりも重要になります。
それでは建設業許可に必要な要件とは、何なのでしょうか?かなり簡単にわかりやすく説明するので、以下の2つの要件だけは、絶対に忘れないようにしてください。
(1)経営業務管理責任者(以下、「経管」と省略)の要件
この要件は、
・建設会社の取締役としての5年以上の経験
・建設業の個人事業主としての5年以上の経験
のいずれかが必要になります。個人事業主が法人成りした場合のように、「建設業の個人事業主」としての経験が3年、「建設会社の取締役」としての経験が2年、(合算して5年以上の経験)でも問題ありません。
とにかく、「建設会社の取締役または建設業の個人事業主の経験が5年以上」と覚えておきましょう。
(2)専任技術者(以下、「専技」と省略)の要件
この要件は、
・建築士や施工管理技士などの国家資格
・電気科や土木科といった特殊な学科の卒業経歴+3~5年の実務経験
・10年以上の実務経験
のいずれかがあれば、満たすことができます。
経管・専技の要件でよくある間違いとして、経管と専技は別々の人でなければならないと勘違いしている方もいるようです。しかし、経管と専技は同一人物でも問題ありません。
たとえば、「社長が経管、国家資格を持っている従業員が専技」といったように、経管・専技を、それぞれ別の人にすることもできます。一方で、ひとり会社の社長のように、社長ひとりで経管・専技の要件を満たすことも可能です。
建設業許可をいますぐにでも取得したいと思ったら、必ず、会社の中に、この2つの要件を満たしている人がいないかどうか?確認をしてみてください。
申請の際には、これらの要件を書面を通して証明する作業が必要になります。
4.必要書類を準備しよう
それでは、3で説明した「経管・専技の要件」を証明するには、どういった書類を準備すればよいのでしょうか?書類の種類を詳細に場合分けして記載していくと「・・・の場合は○○」「・・・に該当しない場合には、○○の他に追加で□□と××」といったように、きりがありません。
そこで、1週間以内になんとか申請まで持ち込みたいみなさんにとって、これだけは必須という特に重要な書類に絞ってご説明させて頂きます。
(1)経管の要件を証明するための書類
経管の要件は、「建設会社の取締役としての経験」が5年以上あると満たすことができます。建設会社の取締役としての5年以上の経験を証明するには、履歴事項全部証明書が必要です。履歴事項全部証明書を見ると「何年何月何日に取締役に就任したのか?」「何年何月何日に取締役を退任もしくは辞任したのか?」が記載されています。
これによって、建設会社の取締役としての5年以上の経験を証明することができます。
経管の要件は、「建設業の個人事業主としての経験」が5年以上ある場合にも、満たすことができます。個人事業主としての5年以上の経験を証明するには、確定申告書を準備する必要があります。個人事業主として建設業を営んでいる以上、確定申告をしていないということはあり得ませんね。税務署に提出していることが分かるように「税務署の受付印があるもの(電子申告の場合には、受付印の代わりにメール詳細があるもの)」の提示が必要になります。
(2)専技の要件を証明するための書類
建築士や施工管理技士などの資格をお持ちの場合には、資格証が必要です。「資格証を紛失してしまった…」という方が稀にいらっしゃいますが、資格証は建設業許可取得の際の大事な書類ですので、紛失することがないように大事に保管しておきましょう。
電気科や土木科といった特殊な学科を卒業している経歴がある方は、卒業証明書や履修証明書の提出が必要になります。
専技の要件は、一定年数の実務経験を経ることによっても満たすことができます。実務経験を証明するには、「請負工事の契約書」「注文書と請書」「請求書と入金通帳」のいずれかが必要になります。この実務経験の証明の仕方については、申請する自治体ごとで取扱いに違いがあるので注意が必要です。
たとえば、「年間で1件」の工事実績を提出すれば、1年間の実務経験が認められるような自治体もあれば、「月1件、年間で12件」の工事実績を提出しなければ、1年間の実務経験が認められないといったように、実務経験の証明のハードルが高い自治体もあります。
このあたりは、自分の申請する自治体のルールをあらかじめ理解しておくと準備がはかどります。また、日ごろから「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」といった書類を、社内でわかりやすいように管理しておくことも重要です。
いざ、申請しようと思ったら、「昔の契約書や請求書や入金通帳を、どこにしまったのかわからない」ようでは、本書で紹介するスピード申請を行うのは難しいといえます。
第2章_建設業許可をスピード取得するためのテクニック
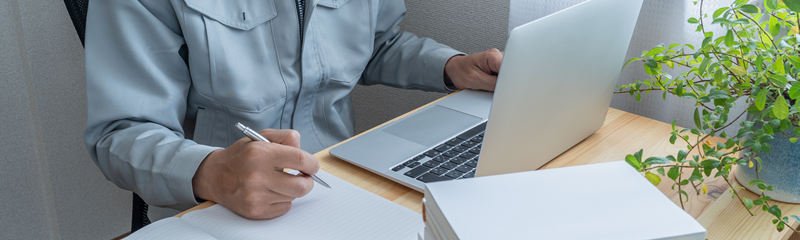
建設業許可を取得するために必要な要件および書類の準備については、ご理解いただけましたでしょうか?
第1章では、1週間以内に建設業許可の申請が必要なときには、何から始めればいいか?について、説明してきました。第2章では、もう少し突っ込んで、スピード申請するためのテクニックについて、解説していきたいと思います。
1.プロテクニックその1 申請までの全体像を正しく理解してゴールを設定する
まずは、申請までの全体像を正しく理解してゴールを設定していきましょう。
ここでいうゴールは、1週間以内に、都庁や県庁に申請書類を提出し受付印をもらうことです。
(1)悪い例
想像してみてください。
『建設業許可に必要な「登記簿謄本」や「納税証明書」を取得して、申請書類を作成して、都庁に書類を提出しに行きました。でも、許可要件を満たしていなかったので、建設業許可を取得することはおろか、申請書類を受け付けてもらうことすらできませんでした』
ということでは、登記簿謄本や納税証明書の取得のために費やした時間や、申請書類の作成のために費やした労力が、すべて無駄になってしまいます。これでは、最短での建設業許可取得というみなさんの目的を達することができません。
(2)理想の手順
建設業許可を取得するには、
・経管と専技の要件の確認
・経管と専技の証明書類の準備
・その他必要書類の準備
・申請書類の作成および申請
といった手順で進めていくのが必須です。私がお客様から実際に建設業許可取得のご依頼を受けた際にも、この手順に則って、作業を進めています。
経管になる人の「個人事業主時代の経験」を証明するのか?「法人役員としての経験」を証明するのか?によって、証明の仕方や必要な書類は変わってきます。
専技にしても国家資格があるのか?特別な学科の卒業経歴があるのか?実務経験しかないのか?によって、証明書類の準備の仕方が変わってきます。
そのため、まずは、要件の確認を行い、その要件を満たすためにどのような証明書類(履歴事項証明書?確定申告書?卒業証明書?)を準備する必要があるのかを把握してください。
次に、「その他必要書類の準備」です。建設業許可申請には、会社の納税証明書や役員の身分証明書など、役所から取り寄せなければならない書類もあります。ある程度、建設業許可取得のための道筋がついたら、できるだけ早い段階で、上記のような法定必要書類を取得するように心がけましょう。
「その他必要書類の準備」が整ったら、最後に申請書類を作成し、申請に行きます。建設業許可の申請には申請手数料として9万円が必要です。また、作成した申請書類は「正本」と「副本」といったように2部持参するのが一般的です。
このように、まずは申請までの全体像を把握するように努めてください。正しくゴールを設定すると、その書類が何のために必要なのか?を理解することができるうえ、次にやらなければならないことが見えてきます。そうすれば、申請の準備のための時間も削減することができます。
2.プロテクニックその2 許可要件を満たしそうにない場合
それでは、現状だと、どうしても経管・専技の要件を満たしそうにない場合は、どうすればよいでしょうか?
・建設会社の取締役としての経験がまだ2年しかない
という場合は、取締役としての経験が3年足りないため、あと3年経たないと建設業許可を取得することができなさそうです。
・工事の実務経験がまだ6年しかない
という場合は、実務経験が、あと4年足りません。そうすると、4年も待たないと、建設業許可を取得することができなくなりそうです。
しかし、元請や取引先に「いますぐにでも建設業許可を取得して欲しい」と催促されているのに「3年か4年待ってください」と答えたのでは、話になりません。みなさんに3年も4年も待っている時間はないはずです。
(1)要件を満たしている人の採用を!
実は、許可要件を満たさない場合でも、経管や専技の要件を満たしている人を会社に招き入れることによって、建設業許可を取得することは可能です。
もし、「みなさん自身が、経管や専技の要件を満たさない」「会社に経管や専技の要件を満たしている人がいない」といった場合でも、経管や専技の要件を満たしている人を採用すれば、よいわけです。
要件を満たしている人の採用は、「能力のある人材を、よりよい条件で会社に招き入れるヘッドハンティング」といったイメージです。
(2)名義貸しには要注意
ここで注意しなければならいなのが「名義貸し」についてです。建設業許可を早く取得したいばかりに、実際は、会社に常勤していないのに、あたかも常勤しているかのように装って申請書類を作成し、名義だけ借りて、建設業許可を取得しようとする人たちもいます。
しかし、建設業許可の取得に限らず、名義貸しは禁止されています。
建設業許可を取得する際には、経管・専技の必要書類として
・健康保険証
・決算報告書の中にある役員報酬一覧
・住民税の特別徴収税額通知書
などの提示が求められる場合があります。「健康保険証に別の会社の会社名が記載されている」「役員報酬一覧に記載されている報酬額が極端に少ない」「住民税の特別徴収がされていない」といった場合には、「経管・専技が常勤していないのではないか?」といった疑いがかけられます。都庁や県庁の審査担当者は、毎日何件もの審査をしているわけですから、誤魔化すことはできません。
経管や専技は、会社に常勤していなければならないため、名義貸しは絶対にご法度です。
もっとも、経管・専技の要件を満たしている人をリクルートすること自体は、建設業許可取得までの期間を大幅に短縮させることになります。もし、現時点で、経管・専技の要件を満たさないという方は、多いに検討すべき方法です。ぜひ、家族、親戚、同僚、知り合いに「過去に建設業を営んでいた方」や、「建設業関連の業務に従事していたことがある方」がいないか?確認を取ってみてください。
3.プロテクニックその3 役所で集める書類と自社書類の整理と取得
建設業許可申請・取得が難しい理由は、いままで説明してきたような「許可要件を理解することが難しい」だけでなく、「準備しなければならない書類が大量にある」ということも挙げられます。そこで、ここでは私なりの書類の整理の仕方を披露させていただきます。
(1)役所から取り寄せる書類・自社にある書類
それは、【役所から取り寄せる書類】と【自社にある書類】の区別という視点です。
都や県の「建設業許可取得の手引き」を見ればわかると思いますが、手引きには必要書類一覧表があります。しかし、この一覧表には、書類が羅列されているだけで、実際には「どこからどうやって取得すればよいのか?どこにあるのか?」が、わからないといった方も多いでしょう。
そこで私は以下のように区分けして整理しています。
【役所から取り寄せる書類】
履歴事項全部証明書/納税証明書/登記されていないことの証明書/身分証明書 など
【自社にある書類】
定款/決算報告書/工事請負契約書/請求書/入金通帳 など
以前、「身分証明書は自分で用意できます」と言って、運転免許証のコピーを都庁に持参した方がいらっしゃいました。しかし、身分証明書とは運転免許証のことではありません。建設業許可取得の際に必要な身分証明書とは、本籍地のある役所から取り寄せる「破産宣告の通知を受けていないことを証明する」ための書類をいいます。
また、「定款のコピーを送ってください」とお願いしたところ「定款はどこから取り寄せればよいのですか?」という質問を受けたこともあります。定款は、役所から取り寄せるものではなく、自社で保管している書類です。会社設立時に作成した「会社の商号・目的や取締役の任期」などが記載された条文形式の書類になります。
このように役所から取り寄せる書類は何か?自社で保管してある書類は何か?といった視点で建設業許可申請のための書類を区分けしていくと、申請のための準備がスムーズに進みます。
(2)役所からの書類の取り寄せ方
役所から取り寄せる書類については、「本人自らが直接取得する方法」と「本人から委任を受けた代理人が取得する方法」といった2つの方法があります。また、「役所の窓口で直接交付を受ける方法」と、「郵送での交付請求を行う方法」があります。
簡単なのは、本人(社長)が各役所に訪問して、窓口で直接、書類の交付を受ける方法です。しかし、この方法だと、本人が忙しい場合や、役所が遠方にある場合には、かえって取得までに時間がかかってしまうことになります。
本人が忙しい場合や、役所が遠方にある場合には、郵送で取得するかもしくは、代理人に取得を依頼するといった方法で、必要書類を取得する方法がお勧めです。
4.プロテクニックその4 社内の担当者を誰にするか?
「1週間以内に建設業許可の申請をしよう」「できるだけ早く建設業許可を取得しよう」と考えた場合、社内の申請担当者を誰にするか?という決断をおろそかにしてはいけません。申請担当者に①時間的余裕があり、②書類の取得・収集・作成など事務処理能力があり、かつ③社内業務に精通している方であれば、手早く申請の準備ができるかもしれません。
しかし、そうでない場合は、1週間どころか準備をはじめて3か月経過するのに、まったく作業が進まないといったケースも少なくありません。
(1)最適な申請担当者は?
たとえば、ひとり社長のような場合はどうでしょう?
社長が朝から晩まで、現場に行っているようなケースだと、書類の収集・作成はもちろんのこと、都庁や県庁への申請も、ままなりません。このような場合は、「奥さまやご家族などの身内に頼む」か、「外部の専門家に依頼する」などしない限り、建設業許可を取得することは、非常に難しいかもしれません。
それでは、従業員が10名以上いるような会社の場合はどうでしょう?このような会社の場合、社長自ら書類を収集したり、作成したりするよりも、事務員や経理担当が、申請担当者として抜擢されることが多いようです。
しかし、このような会社では取締役が複数名いることが多く、取締役に関する必要書類としての「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」などの取得が容易ではありません。また、会社規模が大きい分、過去の工事の件数が多く、工事実績に関する書類作成にも手間がかかることが予想されます。この場合でも、1週間以内の建設業許可申請のハードルは高いです。
(2)社内の雰囲気が悪くなるケースも
どんなに建設業許可を申請しようと思っても、「自分の時間が取れない」「社内担当者が思うように動いてくれない」「業務繁忙のため、まとまった時間がとれない」ということは、よくあることです。
社長にしてみれば「早くしろ!」と言いたいところかもしれません。ですが申請担当者にしてみれば「自ら進んで担当になったわけではない」「そんなに急ぐなら自分でやれば」と、思わぬ対立を生みそうで怖いですね。建設業許可取得のために、社内の雰囲気が悪くなっては、元も子もありません。
このように建設業許可を取得したいものの、どうしても時間がない、やり方がわからず先に進むことができないといった場合にはどうすればよいのでしょうか?
もちろん、精神論を否定するわけではありませんが、気合や根性で乗り切れるほど、建設業許可取得は簡単なものではありません。「餅は餅屋」という言葉がある通り、自分で処理できない問題は専門家に外注するのがベストの選択といえそうです。
第3章_どうしても間に合わない場合には、どうするか?

ここまでお読みいただき、「自分でできそう」と思いましたか?それとも「自分ではできそうにない」と思いましたか?
「自分ならできそう」「自分のちからで何とか許可取得に挑戦してみたい」と思った人は、どうぞ、ご自身でチャレンジしてみてください。うまく行くかもしれません。一方で「ちょっと無理そうだな」と思った人は、迷わず専門家の力を借りることをお勧めいたします。
みなさんに残されている時間は、そう多くはありません。いますぐにでも建設業許可を取得するには、どうすればよいか?第3章で説明いたします。
1.慌てて未整備で申請してしまうとどうなるか?
(1)甘い考え!
「気合や根性で乗り切れるほど、建設業許可取得は簡単なものではありません。」とすでに何回も説明してきましたが、私のお客様のなかでも、かならずと言っていいほど、
・あるものをすべて出せばなんとかなるでしょう
・都庁に行って、ちゃんと口で説明するから大丈夫だよ
と言いだす方がいます。すこし厳しいですが「甘い!」です。そんな考え方で、うまくいった試しがありません。
建設業許可の申請は、書面審査です。どんなに口頭で「10年間実務を経験していました!」とか「法人の代表として5年以上、建設会社を経営していました」と言ったところで、それを証明するための資料(「登記簿謄本」や「請求書・入金記録」など)がなければ、許可を取得することはできません。もちろん、都庁や県庁の職員と喧嘩しても、許可を取得することはできません。
時折いますよね。役所の窓口で、大声を出して怒鳴り散らしている人。どんなに自分の主張が正しくても、それを裏付ける根拠(資料)がなければ、役所としても受付することができません。
「建設業許可を取りたい」といった熱意があることは、わかったとしても、役所が「はい。これで大丈夫です。」といった対応をすることはないと、肝に銘じておいてください。
慌てて未整備のまま申請してしまうと、不足書類を追加で提出するように求められるばかりでなく、最悪の場合、申請書類を受け取ってくれないケースもあります。「体裁を整えてから出直してください!」と言われているようで、なんとも悔しい気持ちになります。
(2)肉体的・精神的な消耗
さらに都庁も県庁も、待ち時間なくスムーズに審査を開始してくれるとよいのですが、私の経験上、番号札を引いてから1時間以上待たされた挙句、そこから審査に1時間以上費やすといった経験も稀ではありません。
現場がある、事務仕事が残っている、会社に戻って経理の仕事をやらなければならないといった状況にある中で、都庁や県庁での2時間以上のロス、往復の時間も含めると3時間以上のロスは、痛すぎます。その日1日で済めばまだよいとしても、「都庁や県庁に行ってはダメだしされ、また、行ってはダメだしされ…」ということを繰り返しているうちに、肉体的にも精神的にも消耗してきてしまいます。最終的に許可を取得できればよいですが、そこまでして許可が取得できないとなると「悲劇」としか言いようがありません。
このような経験をしないためにも、「確実に許可を取得したい」「どうしても急ぎで間に合わせたい」といった場合には、プロ行政書士の活用を検討しましょう。
2.プロの行政書士に依頼するメリット・デメリット
過去に行政書士に何らかの業務を依頼したことがある人や、行政書士と付き合いのある人は、行政書士を活用すると「どういったメリットがあるか?」ということを、ご存知の方も多いと思いますが、ここでは改めて、プロの行政書士を活用するメリット・デメリットについて詳しく解説させて頂きます。
(1)メリット
まず、行政書士は「身分証明書・登記されていないことの証明書といった取締役個人に関する必要書類」「登記簿謄本・納税証明書といった会社に関する必要書類」を、みなさんに代わって、代理で取得することが可能です。そのため、行政書士に依頼すると、ご自身で役所回りをして、書類を収集する時間と手間を省くことができます。
「ただでさえ時間のない忙しい中、役所回りなんて御免だ」という方にとっては、とても大きなメリットです。
次に、建設業許可に強い行政書士であれば、都庁や県庁の審査担当者が「どういったところをより詳しく注意して見ているのか?」という点について的確に把握しています。そのため、大事なところとあまり大事でないところの見極めが、非常にうまいです。
素人の方は、申請書類は「どれも一律に重要」と考えがちですが、私のように建設業許可申請の経験が多くなると「ここの記載は正確に書いた方が良い」とか「ここの数字は、大体でよい」といったメリハリがわかってきます。つまり、役所に対する申請書類の見せ方にたけているのです。
そのため、みなさんは、「行政書士の指示に従って書類を準備するだけ」で、ご自身が書類準備にかける労力や書類作成にかける時間を、格段に減らすことができます。ご自身で申請する場合には、手引きに忠実に1つ1つ書類を精査しなければならなかったところ、行政書士に依頼することによって、そういった手間が省けるのです。
(2)デメリット
一方で、プロの行政書士に依頼する1番のデメリットは、費用負担にあると言えます。
行政書士に依頼する場合には、都庁や県庁へ支払うの法定の手数料(9万円)以外に、行政書士への報酬が必要になります。相場としては15~30万円程度に設定している行政書士事務所が多いようです。
そのため、みなさんの中には、「自分でやればタダ、行政書士に依頼すれば30万円程度の出費」と、行政書士への依頼を躊躇してしまう方がいるかもしれません。
しかし、こういった考え方はできないでしょうか?
建設業許可は一度取得すれば5年間有効です。仮に30万円の行政書士報酬を支払ったとしても、年間6万円、月に換算するとひと月5千円にしかなりません。
建設業許可を取得すれば、向こう5年間に渡って、500万円以上の工事を受注できるわけですから、投資の額としての月々5千円の出費は、微々たるものです。
行政書士に依頼するメリット・デメリットは、他にもあるかもしれませんが、最終的には、「費用負担をどう捉えるか?」ということに行きつくかと思います。この投資をケチって自分で申請するか?それともプロに任せるか?
まさに、みなさんの経営判断が問われるところです。
3.建設業許可に強い行政書士の見極め方
それでは、みなさんが実際に行政書士に建設業許可申請を依頼する場合、建設業許可に強い行政書士をどうやって見極めればよいのでしょうか?
もちろん、みなさんの周りの知り合いや、付き合いのある顧問税理士に紹介を頼んでもよいと思います。ただし、紹介された行政書士が「建設業許可に強い」か否かは、疑問です。
実際に、「顧問税理士から紹介された行政書士に相談してみたけど、許可を取得することができなかった」と言って、弊所に相談に見える方もいらっしゃるくらいです。
そこで、私は、以下の2つの方法で、建設業許可に強い行政書士を見つけることを提案いたします。
(1)インターネットで検索し、申請実績を確認してみよう!
まず、手っ取り早いのが、インターネットでの検索です。ネット検索なら、パソコンさえあれば、空いている時間に、すぐにでも、できてしまいますね。建設業許可に強い行政書士であれば、必ずといっていいほど、専門知識と豊富な申請実績を掲載しているはずです。
たとえば私の事務所の場合、令和4年6月の時点で全65件の建設業許可関連の申請実績をホームページ上に掲載しています。
どれも、正真正銘、お客様からご依頼を受けて、実際に申請を通したものばかりです。
このように建設業許可の要件である「経管」や「専技」の専門的知識の解説はもちろんのこと、「どれだけわかりやすく、かつ詳細に、過去の申請実績について解説できているか?」といった点が、実力のある行政書士の見分け方として重要なポイントになるかと思います。
ホームページ上に公表されている「建設業許可を取得した過去の申請実績」の中で、みなさんと同じような状況にある会社の申請実績が詳細に掲載されていれば、そこの事務所が、依頼先の有力候補になることは間違いありません。
(2)具体的な質問を投げかけてみよう
インターネットで検索したあとは、実際に具体的な質問を投げかけてみましょう。
たとえば「建設業許可を取りたいのですが、どうしたらよいですか?」といった質問は抽象的過ぎて絶対にNGです。また「許可を取得するための書類を教えてください」というのもダメです。それこそ、「自分で調べてください」となってしまい、その行政書士が建設業許可に強いか否かを見極めることなく、話が終わってしまいます。
みなさんは、絶対にこのような聞き方をしないようにしてください。
できるなら、「東京都の○○工事業の建設業許可を取りたいです。取締役に就任してから、もうすぐ5年が経ちます。従業員が持っている○○という資格で許可を取得することはできますか?」といった具合に、具体的な質問を投げかけるようにあらかじめ質問内容を整理しておきましょう。こういった質問をするには、当然のことながら、みなさんにも事前知識が必要です。このような具体的な質問に対して、簡潔に回答が返ってくるようであれば、その行政書士は建設業許可の経験が豊富な「建設業許可に強い行政書士」であると言えるでしょう。
4.さあ、いますぐ判断して行動しよう
このページもいよいよ残すところわずかとなりましたが、「建設業許可を取得するには、どうすればよいか?」といった疑問、「1週間で申請するには、何からはじめればよいか?」といった疑問は、すこしは解消できましたか?
(1)みなさんに参考にして欲しい申請実績
私の事務所では、いままで数多くの建設業許可の申請を代行してきました。
- 個人事業主から法人成りして、2週間で許可申請までたどりついた会社
- リフォームや原状回復工事を行うため10年の実務経験を証明して内装工事の建設業許可を取得した不動産会社
- はじめての建設業許可で、いきなり特定建設業許可を取得した会社
- 機械工学科という特殊な学科の卒業経歴を使って、管工事の建設業許可を取得することに成功した空調設備会社
- 建築科の卒業経歴を使って、内装工事の建設業許可を取得することに成功した宅建業者
- 電気通信工事と電気工事の2業種を同時に取得した電気会社
- 経管、専技を外部から招聘し、工事経験がないにもかかわらず建設業許可を取得することに成功した不動産会社
- 「個人事業主としての3年の経験」+「代表取締役としての2年の経験」を証明し、防水工事業の建設業許可取得に成功した会社
そのほか、10年の実務経験を証明し建設業許可を取得した事案など、枚挙にいとまがありません。申請実績の一部を弊所ホームページに掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください
(https://www.shinjuku-kensetsu.jp/jisseki-ichiran)。
「建設業の新規許可取得」に関しては20件以上、「工事業種の追加」「10年の実務経験の証明」「経管・専技」に関する申請実績と合わせると、60件(令和4年6月現在)を超える申請実績を掲載しています。これからもどんどん、増えていく予定です。みなさんが建設業許可を取得する際の参考にしていただければ幸いです。
(2)まずは、最初の一歩を踏み出してみましょう!
建設業許可を取得できた方々と、みなさんのように建設業許可を取得できないで困っている方との違いは何だと思いますか?
何千万円という公共工事を落札している会社も、何億円という売上がある会社も、最初は、いまのみなさんと同じように、建設業許可取得について、学んでいたに違いありません。
頭の良さ?努力の量?建設業許可取得に対する熱意?
どれも正解かもしれませんが、たったひとつの違いは、行動したか否かです。すくなくとも、建設業許可を取得できた会社は、きちんと正しい方法で正しい努力を行ってきた人たちです。ずば抜けて勉強したとか、努力したとか、そういったことではなく、まずは、建設業許可取得に向けて、なるべく早く、行動を起こしたからこそ、みなさんに比べて早く建設業許可を取得できているにすぎません。
はっきり言って、次はみなさんの番です。
建設業許可を取得できるか否かは、いまのみなさんの行動にかかっています。
行動を起こすために必要な最低限の知識は、このホームページにすべて記載しています。建設業許可取得への道は、いばらの道かもしれませんが、まずは、勇気を出して、最初の一歩を踏み出してみましょう!
おわりに 「もう無理かも…」と相談に来たある建設会社の社長の話
最後に、私の事務所に相談に来て、無事、建設業許可を取得した会社の事例をご紹介させていただきます。
その社長が弊所にお越しになったときのことは、とてもよく覚えています。
「もう無理かもしれない…」「毎晩、眠れない…」とかなり疲労困憊のようでした。
—————————————
元請会社からの強い要望により、建設業許可を取得しなくてはなりません。以前から、それとなく許可を取得するように催促されていたのですが、いよいよ「許可がない以上、現場に、入れることはできない!」と最後通告を受けてしまいました。
顧問税理士から紹介された行政書士に相談したのですが、「実務経験の証明が難しいので建設業許可は取れませんね」と断られてしまいました。
—————————————-
という経緯です。
頭を抱えて、私の事務所にやってきたのはいうまでもありません。インターネットで「なにか情報はないか?」と検索しているうちに、うちの事務所のホームページにたどり着いたとのことでした。
早速、実務経験を証明するため銀行通帳を確認したところ、請負工事の入金記録がきちんと10年分残っていました。「これなら行ける!」と判断し、スタッフ総出で必要書類を収集、入金記録と請求書を突合し、相談から1週間後に都庁へ申請に行きました。結果、無事申請が受け付けられて建設業許可を取得することができました。
このように建設業許可の取得は、だれに頼んでも同じではありません。専門知識のある経験豊富な行政書士に依頼をすれば、結果が違ってくるかもしれないのです。もし、この社長が前任の行政書士のところであきらめていたら…、私の事務所ではなく他の事務所に相談しに行っていたら…、建設業許可を取得することなく、文字通り「現場から締め出されていた」かもしれません。
どうか、みなさんも最後まであきらめずに「何か方法がないか」試してみてください。そして、いますぐアクションを起こしてください。
「どうしても身近に頼める人がいない」「だれに相談したらよいわからない」というお困りの場合は、弊所までご連絡ください(https://www.shinjuku-kensetsu.jp/gyoumu-irai)。
「建設業許可取得の可能性」「取得のために必要な書類」「手続きの流れ」などについて、ご案内させていただきます。
それでは、みなさんの1日でも早い建設業許可取得を祈念して、終わりにしたいと思います。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。













