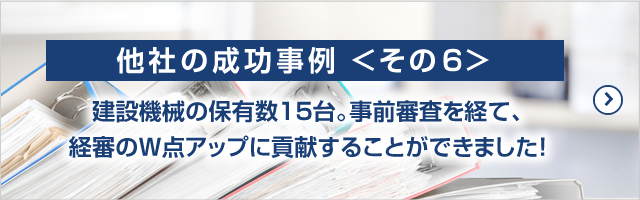
経営事項審査を受けている皆さんの中には、トラクターやダンプなどの建設機械を保有されている方も多いと思いますが、経審の申請の際に、きちんと申告できていますでしょうか?
トラクター・ダンプ・ショベル系掘削機などの建設機械を保有している会社のほうが、経営事項審査の点数が高いです。これは「建設機械を地震や洪水などの災害発生時に、緊急的に使用できる」といった地域の防災の観点から、建設機械の保有状況が、経審における「社会性等:W点」の審査項目となっているからです。
このページでは「建設機械を15台保有している会社」の申請実績をご紹介するとともに、「申請の際の注意点」や「W点」について解説していきたいと思います。
相談:前任行政書士から経審の申請手続を引き継いで欲しい
会社の概要
| 会社所在地 | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 業種 | 土木・舗装工事 |
相談内容
| 相談内容 | 前回まで経審を担当していた行政書士の先生が、都合により業務を継続できなくなってしまったとのこと。前任者を引き継ぐ形で、経営事項審査をはじめとした許認可の申請をお願いしたい。 |
|---|
申請内容
| 申請内容 |
|
|---|
行政書士法人スマートサイドの対応
前任の行政書士の先生から「個人的な都合で業務を行えなくなってしまったので、経審を引き継いでくれる行政書士事務所を探している」とのご連絡をいただきました。
まずは、会社を訪問し社長にご挨拶の上、前回までの経審の受審状況について、確認をいたしました。建設業許可を取得してから20年以上経っており、経審もずっと受審されてきていたようです。また、世田谷区の道路舗装の入札案件も年に数件程度、落札できているようでした。
過去の経審の申請状況や東京都庁建設業課への届出書類(副本)を、すべてお預かりし事務所に戻って、確認作業をしました。
漏れや、不備などは特になかったので、前任者の行政書士の先生から引き継ぐかたちで、弊所で経営事項審査の申請をはじめとした建設業許可申請業務について、担当する運びとなりました。
「経営事項審査」と「建設機械の保有状況(W点)」の解説
経営事項審査における建設機械の保有状況
経営事項審査の際に、建設機械を保有していると有利になるということは、何となくわかっている方も多いと思いますが、
- どういった理由で
- どのように
点数が加点されるかをご存じの方は多くはないと思います。また、その際の
- 確認資料
- 注意点
となると、よほど経審を専門にやっている行政書士でない限り、正確に理解することは難しいといえます。
「建設機械」といっても、何でもよいわけではありません。また、どんなに「建設機械を保有している」と言っても、実際にその保有状況を証明できなければ、経審の加点事由にはなりません。
そこで、以下では、弊所が受任した上記事案をモデルにして、「建設機械の経審での評価のされ方」「評価対象となる建設機械の種類」「裏付け資料」などについて見ていきたいと思います。
評価対象となる建設機械の種類
(1)評価対象となる建設機械
経営事項審査の際に、加点事由となる建設機械は以下のものに限られます。建設機械であれば、なんでもよいというわけではありません。
御社が保有している建設機械の中に、該当するものがないかどうか?確認をしてみてください。
| 種類 | 名称 | 範囲 |
|---|---|---|
| 掘削機械 | ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
| トラクター類 | ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの |
| トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの | |
| 整地・締め機械 | モーターグレーダー | 自重が5トン以上のもの |
| 大型自動車
(大型ダンプ車) |
土砂等を運搬する大型自動車のうち最大積載容量が5トン以上又は車両総重量が8トンを超えるもの | |
| 移動式クレーン | つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン |
※注意※
令和5年1月から、加点対象となる建設機械の種類が追加されました。最新の状況は、手引きなどで必ず確認して頂くようにお願いします。
(2)今回申請したお客様の場合
このお客様の場合、上記に該当する建設機械が15台ありましたので、15台すべてを建設機械保有状況一覧表に記載して、経審を受審しました。建設機械保有状況一覧表の書き方については、手引きにも記載がありますので、ぜひ確認をしてみてください。
今回の、お客様の内訳は以下の通りです。
| 種類 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| ショベル系掘削機 |
1台 (KOMATSU) |
ショベル系掘削機のうちのショベル |
| モーターグレーダー |
1台 (SUMIMOTO) |
自重7510kg |
| トラクターショベル |
5台 (KOMATSU) |
すべてバケット容量は0.4立方メートル以上 |
| ダンプ |
8台 (いすゞ) |
すべて最大積載容量5トン以上 |
| 合計 | 15台 | 15台すべて経審の加点事由となる基準を充足 |
評価対象となる建設機械の裏付け資料
先ほども記載しましたが、仮に上記のような建設機械を所有またはリースしていたとしても、「(1)本当に所有またはリースしていること」「(2)基準を充足していること」を証明できなければ、経審の際の加点にはなりません。
では、どういった資料で、証明すればよいのでしょうか?証明の方法は、2段階になっています。
- まずは、契約書類等で「所有」または「リース」の状況を確認します。
- 次に、その建設機械が「経審の基準を満たすか」を確認します。
それでは、証明書類について具体的に見ていきます。
(1)所有またはリースの状況
まずは、「本当に建設機械を所有またはリースしているか」の確認資料です。当たり前ですが、他社が所有・リースしている建設機械は、御社の経審の加点事由になるわけがありません。あくまでも、御社(申請会社)が、所有またはリースしている建設機械であることが前提です。
なお、所有であってもリースであっても、加点状況に変わりはありません。以前、「所有のほうがリースより評価が高い」と勘違いされている方がいましたが、所有とリースとで評価基準に変わりはありません。
| 所有の場合の確認資料 | ||
|---|---|---|
| (ア):売買契約書
(イ):(ア)がない場合は、注文書、申込書、販売(譲渡)証明書 (ウ):(ア)も(イ)もない場合は、法人税確定申告書別表16及び償却台帳 |
| リースの場合の確認資料 | ||
|---|---|---|
| (ア):リース契約書
(イ):(ア)がない場合は、リース契約の証明書 |
(2)経審の基準を満たすか?
(1)の契約書や注文書で、本当に建設機械が御社の所有またはリースであることを確認した後は、その建設機械が経審の評価基準を満たすか?(言い換えると前掲した「評価対象となる建設機械の表」の要件を満たすか?)を証明しなければなりません。
その際の証明資料は、以下の通りです。
| 建設機械の種類 |
裏付資料(確認事項) |
|---|---|
| ショベル系掘削機 |
|
| ブルドーザー | |
| トラクターショベル | |
| モーターグレーダー | |
| 大型ダンプ車 |
|
| 移動式クレーン |
|
(※注1)労働安全衛生法上、1年以内に1回の特定自主検査の受検が義務付けられているため、原則として提示する必要がありますが、新品については、納入から1年以内に自主検査を受検すればいいので、特定自主検査実施時期証明書(写し)などの提示で足ります。
(※注2)ショベル系掘削機の場合は、特定自主検査記録表を掘削機専用の様式で作成していれば、ショベル系掘削機であることの確認ができるので、カタログなどは不要です。
(3)今回申請したお客様の場合
・所有またはリースの状況の確認資料について
今回申請したお客様の場合、15台中13台が所有、2台がリースという内訳でした。
「(1)所有またはリースの状況」については、いずれも、(ア)に該当する「売買契約書」および「リース契約書」をお持ちでしたので、売買契約書およびリース契約書のコピーを、所有またはリースの確認資料として提示をしました。
・「経審の基準を満たすか?」の確認資料について
「(2)経審の基準を満たすか?」の確認資料については、ショベル系掘削機1台、モータグレーダー1台、トラクターショベル5台の合計7台については、「特定自主検査記録表」と「カタログ」を提示しました。
但し、ショベル系掘削機については、特定自主検査記録表の様式でショベル系掘削機であることがわかるので、カタログは提示していません。また、トラクターショベルのうち1台が、購入1年以内の新品でしたので、この新品については、特定自主検査記録表ではなく、特定自主検査実施時期証明書の写しを付けました。
残りのダンプ8台については、自動車検査証およびカタログを提示しました。
申請する際の注意点
この事案では、上記のような証明資料を提示して、15台の建設機械のすべてについて、保有が認められ経営事項審査の「社会性:W点」ひいては「総合評定値:P点」をアップすることができました。
仮に、御社の保有する建設機械の台数が1~2台であれば、それほど面倒ではありませんが、15台ともなると準備の際に注意しなければならない点がいくつかありませす。
そこで以下では、特に今回の事案のように建設機械の保有台数が多い場合の注意点について、記載していきたいと思います。
注意点その1:事前審査を受けましょう!
この点については、東京都の経営事項審査の手引きにある通りですが、建設機械の保有台数が6台以上の場合には、事前審査を受けなければなりません。
これは、経審の審査時間を短くするためです。本件のように建設機械が15台もある場合、限られた審査時間で、すべての建設機械について細かくチェックすることは、困難です。仮にチェックできたとしても、審査に時間がかかりすぎてしまいます。
そのような審査側(都庁側)の都合から、建設機械の保有が6台以上の場合には、経審の1か月程度まえに、建設機械に関する必要書類を準備して事前審査を受けるように求められています。
この事前審査については、意外と見落としがちなので、必ず、忘れないようにしましょう。なお、「技術職員数が多い場合」や「工事経歴書の裏付け資料の確認に時間がかかる場合」など、経審の前に事前審査を受けるように求められている事項は、「建設機械の保有台数が6台以上」の場合以外にもありますので、確認が必要です。
注意点その2:確認資料の日付に注意しましょう!
今回の事案のように、15台すべての建設機械の保有を認めてもらうには、確認資料に記載のある日付について、注意をする必要があります。
売買契約書・リース契約書の日付
まず、売買契約書またはリース契約書の日付については、審査基準日前でなければなりません。審査基準日後に購入した建設機械は、今回の経審の評価対象にはなりません。経営事項審査は、あくまでも審査基準日(直前の確定した決算)を基準に審査を行いますので、売買契約書およびリース契約書の日付には注意をしてください。
車検証の有効期間
車検証についても同様に、車検証の有効期間に注意する必要があります。審査基準日時点(直前の確定した決算の時点)で、車検証が有効である必要があります。例えば、令和3年3月31日が決算(=審査基準日)であるならば、令和3年3月31日時点で有効な車検証を提示する必要があります。
車検証については、ついつい、直近の一番新しいものを用意しがちですが、あくまでも審査基準日を基準に判断しますので、審査基準日現在で有効なものを用意して下さい。
特定自主検査記録表の検査年月日
特定自主検査記録表については、審査基準日以前1年以内に点検を実施し、建設機械が正常に稼働することが必要です。これは、労働安全衛生法上、1年以内に1回の特定自主検査の受検が義務付けられているからです。
審査基準日以前1年以内に点検が実施されていないと、経審の評価対象にはなりません。例えば、令和3年3月31日が決算(=審査基準日)であるならば、令和2年4月1日~令和3年3月31日の間に、検査を受けていなければなりません。
経審の前に慌てて検査を受けたとしても、検査を受けた日が令和3年4月1日以降であれば、前述の「審査基準日以前1年以内」といった条件に該当しないので、この場合には、今回の経審の評価対象になりません。
ショベル系掘削機や、モーターグレーダーなどの建設機械については、1年に1回の検査を忘れないように注意しましょう。
注意点その3:売買契約書やリース契約書の保管に注意しましょう!
建設機械の「所有」を証明するには、「売買契約書」が必要です。仮に、「売買契約書」を紛失してしまった場合でも、
- 法人税確定申告書別表16
- 償却台帳
によって、「所有」の状況を証明することができます。しかし、償却台帳の中から該当の建設機械を見つけ出すのは、すこし手間がかかります。さらに、実際の建設機械の名称と、償却台帳に記載されている名称表記とが、異なる場合、本当にこの機械を保有しているのか?について、疑義が生じる場合もでてくると思います。
建設機械の所有を証明するには「売買契約書」が一番適していますので、売買契約書などの書類は大事に保管するように注意してください。
建設機械の保有状況がW点に与える影響
それでは、今回申請したお客様のように、建設機械を保有していると経営事項審査で、どれだけ点数アップが期待できるのか?見ていくことにしましょう。この点が、皆さんの一番興味がある部分かもしれませんね。
総合評定値P点の算出方法
まず、経審の結果であるP点は、下記の数式によって算出されます。
| 総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W) |
W点(その他社会性)の構成
このうち、建設機械の保有状況は、W点で評価の対象になります。W点の構成は以下の通りになっています。W7が建設機械の保有状況の点数になります。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| W1 | 労働福祉の状況の点数 | |
| W2 | 建設業の営業年数の点数 | |
| W3 | 防災協定締結有無の点数 | |
| W4 | 法令遵守の状況の点数 | |
| W5 | 建設業の経理状況の点数 | |
| W6 | 研究開発の状況の点数 | |
| W7 | 建設機械の保有状況の点数 | |
| W8 | 国際標準化機構が定めた規格による登録状況の点数 | |
| W9 | 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の点数 | |
| W10 | 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況の点数 | |
| 上記(W1~W10の点数の合計)×10×190÷200 | ||
W7:建設機械の保有状況の点数
では、さらに、建設機械の保有状況の点数(W7)は、どのような方法で算出するのでしょうか?建設機械の保有状況の点数(W7)は、保有台数ごとに下記の点数が与えられることになっています。
| 建設機械の所有及びリースの台数 | 点数 | |
|---|---|---|
| 15台以上 |
15点 |
|
| 14台 |
15点 |
|
|
13台 |
14点 |
|
|
12台 |
14点 |
|
| 11台 | 13点 | |
| 10台 | 13点 | |
| 9台 | 12点 | |
| 8台 | 12点 | |
| 7台 | 11点 | |
| 6台 | 10点 | |
| 5台 | 9点 | |
| 4台 | 8点 | |
| 3台 | 7点 | |
| 2台 | 6点 | |
| 1台 | 5点 | |
| 0台 | 0点 | |
表を見ていただくとわかると思いますが、建設機械を1台でも保有しているとW7の評点が5点もらえます。一方で、W7の評点は、最大でも15点なので、仮に建設機械を15台以上持っていたとしても、W7の点数は15点がMAXということになります。
建設機械の保有台数が15台の場合と0台の場合との比較
本件のお客様のように、建設機械の保有台数が15台ある場合、W7の点数は15点になる一方で、仮に建設機械の保有台数が0台の場合、W7の点数は0点になります。
| W点=(W1~W10の点数の合計)×10×190÷200 |
W点を算出する上記の計算式にあてはめてみましょう。W7が「0点」と「15点」の場合では、
- 15×10×190÷200=142点(※小数点以下切り捨て)
W点で142点もの違いが出てきます。
| 総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W) |
総合評定値P点は、W点×0.15ですから、P点換算をすると
- 142×0.15=21(※小数点以下四捨五入)
建設機械の保有台数15台と0台では、P点で21点もの違いが出てきます。
本事案の「社会性:W点」および「総合評定値:P点」
本事案の「社会性:W点」
本件の場合、W点の内訳は以下の通りでした。
| 項目 | 内容 | 本件 | |
|---|---|---|---|
| W1 | 労働福祉の状況の点数 | 30点 | |
| W2 | 建設業の営業年数の点数 | 38点 | |
| W3 | 防災協定締結有無の点数 | 0点 | |
| W4 | 法令遵守の状況の点数 | 0点 | |
| W5 | 建設業の経理状況の点数 | 0点 | |
| W6 | 研究開発の状況の点数 | 0点 | |
| W7 | 建設機械の保有状況の点数 | 15点 | |
| W8 | 国際標準化機構が定めた規格による登録状況の点数 | 0点 | |
| W9 | 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の点数 | 0点 | |
| W10 | 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況の点数 | 0点 | |
| W1~W10の合計=83点 | |||
上記の内訳からW1~W10の合計を算出すると83点になるので、W点は788点になります。
| W点=83×10×190÷200=788(※小数点切り捨て) |
本事案の「総合評定値:P点」
さらに本件の場合のW点以外の評点は下記の通りでしたので、
- X1=918点
- X2=738点
- Y=509点
- Z=643点
- W=788点
すべての点数を総合評定値P点を算出するための計算式にあてはめると、本件の総合評定値P点は721点になります。
| 総合評定値(P)=918×0.25+738×0.15+509×0.20+643×0.25+788×0.15
=229.5+110.7+101.8+160.75+118.2=721(※四捨五入) |
建設機械の保有が仮に0台だった場合、P点に換算すると21点ものマイナスになるので、建設機械の保有がP点アップに大きな影響を与えたことは間違いないと思います。
建設機械の保有台数15台の経審を終えて…
本件は、前任行政書士からの引継ぎ案件でした。弊所が経審を担当することになって、
- お客様の準備の負担軽減
- 申請までのスピードアップ
を計ることができたと自負しています。また、建設機械の保有台数が15台と多かったものの、お客様のほうで、「売買契約書・リース契約書」「特定自主検査記録表」「車検証」といった書類をすべてわかりやすく保管してくださっていたことから、申請にあたって大きな支障も生じることなく比較的スムーズに準備できた事案だったと思います。
経営事項審査でお困りのご担当者さまへ
このページでは、建設機械の保有状況がW点、ひいてはP点にどのような影響を与えるか?といったとてもマニアックな事柄を解説させて頂きましたが、参考になりましたでしょうか?
行政書士法人スマートサイドでは、行政書士の切り替え案件にも対応しています。この会社のように、前任の行政書士からの引継ぎや、会社のご担当者さまからの引継ぎにも柔軟に対応しています。
経営事項審査で気にするべき点は、何も、建設機械の保有台数ばかりではありません。技術職員名簿の作成や完成工事高の割振りなど、実にさまざな数字に配慮しなければなりません。
もし、経営事項審査の申請でお困りの人がいれば、ぜひ、下記問い合わせフォームから行政書士法人スマートサイドまで、ご相談下さい。













