
「建設業許可を新規に取得したり、建設業許可の業種を増やしたい」と思った時に、
- うちの会社には、技術者の資格を満たす人はいるのかな?
- どういった資格を持っている人を雇えばよいのかな?
- 知り合いに「二級」の国家資格を持っている人ならいるのだけど?
と、『技術者の資格』の要件で悩まれる方は多いです。
もしかして、御社も『どんな資格があれば、許可を取れるのか?』考えているのかもしれませんね。また、「一級」の国家資格を持っている人は、なかなか見つからないにしても、「二級」の国家資格であれば、ご自身で取得したり、もっている人が身近にいたりして、意外となんとかなるかもしれません。
そこで、このページでは、「二級の土木施工管理技士」「二級の建築施工管理技士」の資格に焦点を当てて、「二級の施工管理技士」の資格を持っていると、どんな建設業の許可を取得することが可能になるのかについて、記載していきたいと思います。
また、「二級土木施工管理技士」「二級建築施工管理技士」の資格も細かく見ると3つの種別に分かれています。その種別ごとに取得できる建設業許可の業種も変わってきます。
二級土木施工管理技士の場合
二級土木施工管理技士は、以下の3つの種別に分かれています。
- 土木
- 鋼構造物塗装
- 薬液注入
一般的には、「土木」の種別をお持ちの方が多いようです。「鋼構造物塗装」や「薬液注入」は、あまりお見かけしないマイナーな種別です。
二級建築施工管理技士の場合
二級建築施工管理技士も土木の場合と同様に、その中身は3種類の種別に分かれています。
- 建築
- 躯体
- 仕上げ
下記に記載していますが、同じ「二級建築施工管理技士」でもその種別が「建築」「躯体」「仕上げ」のいずれかによって、取得できる建設業許可が異なりますので、ご注意ください。
それでは、「二級土木」や「二級建築」の資格を持っていることによって、それぞれ、どの建設業許可を取得できる可能性が出てくるのでしょうか?
二級土木施工管理技士の場合
1.「土木」の場合
二級土木施工管理技士(土木)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
- 土木一式工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 鋼構造物工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 水道施設工事
2.「鋼構造物塗装」の場合
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
- 塗装工事
3.「薬液注入」の場合
二級土木施工管理技士(薬液注入)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
- とび・土工・コンクリート工事
二級建築施工管理技士の場合
1.「建築」の場合
二級建築施工管理技士(建築)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
- 建築一式工事
2.「躯体」の場合
二級建築施工管理技士(躯体)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
- 大工工事
- とび・土工・コンクリート工事
- タイル工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
3.「仕上げ」の場合
二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
- 大工工事
- 左官工事
- 石工事
- 屋根工事
- タイル工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装工事
- 熱絶縁工事
- 建具工事
通常の場合
二級土木施工管理技士の国家資格を持っていない場合、「専任の技術者」になるためには、『10年間』の実務経験を証明しなくてはなりません。
例えば
- 厚生年金被保険者記録照会回答票
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書
- 契約書、請求書、入金通帳
など期間10年分の資料を提示することが必要になります。
二級施工管理技士の国家資格を持っている場合
二級施工管理技士の国家資格を持っている場合、10年の実務経験の証明は必要ありません。国家資格の合格証を提示するだけで、上記のような資料の提出は必要ありません。以上のように、二級施工管理技士の資格を持っている方が、新規に建設業許可を取得するにしても、新たに建設業許可業種を増やすにしても『圧倒的』に作業量が減ります!!
資料を捨ててしまったとか、何らかの事情で過去の10年間の資料の提出ができないとか、そもそも10年間の実務経験なんてないといった方には、二級施工管理技士の資格を取得することをお勧めいたします。
「名義貸し」について
二級建築施工管理技士、ないしは二級土木施工管理技士を採用することによって、建設業許可を新たに取得したり、建設業許可業種を増やすことができる可能性はあります。もっとも、その方は、専任技術者として御社に「常勤」することが前提です。常勤とは、おおよそ9時~18時くらいまで、御社に勤務していることを言います。常勤である以上、月の給料が数万円ということはあり得ません。「週2~3日の出勤で、月の給料数万円」だと、常勤性は認められず、名義貸しではないかと疑われてしまいます。
「社保加入」について
御社への常勤を確認する資料として、求められるのが「(事業所名が入っている)健康保険被保険者証のコピー」です。健康保険証に事業所名が入っていない場合には、「厚生年金被保険者記録照会回答票」や「住民税特別徴収税額通知書」が常勤性の証明資料になります。新たに採用した二級施工管理技士の方には、御社の社会保険に加入していただく必要があります。
「他社での登録」について
これも、常勤性の要件と関連します。御社に常勤している社員である以上、他社で常勤しているということはあり得ません。よくあるのが、新たに採用した人が、他の業者で「専任技術者」として登録されていたというケースです。複数の会社で常勤することがあり得ない以上、他の業者での「専任技術者」としての登録を抹消しない限り、御社の「専任技術者」にはなることはできず、御社で建設業許可を取得することもできません。本人も気づいていない場合があるので、注意しましょう。
「合格証の原本」について
まれに、合格証をなくしてしまうお客様がいらっしゃいます。試験に合格したのが、何十年も前のことだと、合格証を紛失してしまうのも無理はありません。ですが、建設業許可を取得する際には、合格証の写しが必要です。どんなに合格した事実があったとしても、その事実を証明できなければ、建設業許可を取得することはできません。合格証は再発行できますが、1カ月から2カ月くらいかかることもあるようです。いざというときにいつでも提示できるように、合格証は大事に保管しておきましょう。
建設業許可取得でお困りの際は行政書士法人スマートサイドへ
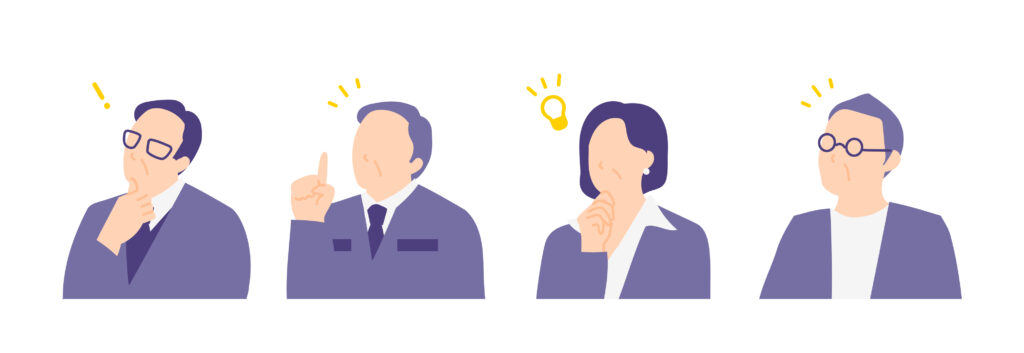
✅ 建設業許可を持っていないと現場に入ることができない
✅ 元請から建設業許可の取得を催促されている
✅ 500万円以上の工事の受注ができなくて困っている
という話をよく聞きます。徐々にですが、「建設会社にとって、建設業許可を持っていることが、スタンダードになりつつある」ようです。以前までは、建設業許可を持っていることがアピールポイントでしたが、現在では、持っていることが当たり前という状況になっています。
もし仮に御社が「建設業許可を持っていない会社」「建設業許可を取得できない会社」であるとすると、今後、ますます、厳しい状況になっていくかもしれません。
行政書士法人スマートサイドは、東京都内にある建設業許可取得の手続きに特化した行政書士事務所です。施工管理技士のような資格を持っている会社の建設業許可取得手続きはもちろんのこと、資格を持っていなくても実務経験を証明するなどして、数多くの建設会社を許可取得に導いてきた実績があります。
建設業許可を取得する手続きは、誰にでもできる簡単な作業ではありません。建設業許可を取得するにしても、新たに許可業種を増やすにしても、必要書類を集めたり、申請書類を作ったり、都庁まで提出しに行くことは、とても手間のかかる大変な作業です。しかも、新たに「二級建築施工管理技士」ないしは「二級土木施工管理技士」を採用したうえで、建設業許可を取得するとなると、
- 本当に建設業許可がとれるのかな?
- 手続上、これであっているのかな?
- 採用したのに、許可が取れなかったらどうしよう?
とさまざまな疑問がわいてきます。自分で手引きやマニュアルを読んで申請するよりも、専門家に手続きを依頼したほうが断然早いですし、確実です。「二級施工管理技士の資格を持っている」「二級施工管理技士の資格をあらたに取得した」「二級建築施工管理技士の資格者を採用した」という人で、「建設業許可の取得を考えている」という人がいれば、どういった手続きで建設業許可を取得することができるのか?について、最適なご提案をさせて頂くことが可能です。
お困りの際はぜひ、ページ下部にある問い合わせフォームからご連絡下さい。













