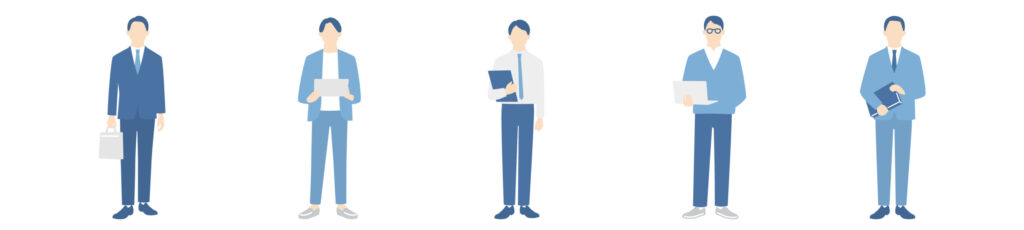-1024x538.jpg)
✅ 受注する工事金額の上限が超えそうだから特定建設業許可にしたい
✅ 一級の資格を持っている技術者を採用したので、特定に変えたい
✅ 公共工事を受注するにあたって、特定建設業許可が必要
✅ 取引先から特定建設業許可を取得するように言われた
ということで、困ってはいないでしょうか。そもそも、建設業許可の種類の中に「特定」と「一般」があるのを知らなかったり、「一般」を「特定」に切り替える方法を知らなかったりと、わからないことだらけで、インターネットで情報収集をしているのかもしれませんね。
弊所は、東京都で建設業許可取得を専門に行っている行政書士事務所です。弊所には、「建設業の許可を取得したい」というお客様からの依頼と同様に、「今持っている許可を、特定建設業許可に変えたい」といったお客様からのお問合せを多数いただいております。
通常「建設業の許可」と言われている一般建設業許可に比べて、馴染みが薄いせいか、特定建設業許可取得のための特殊な要件や、特定許可業者に生じる義務について把握していらっしゃる方は、少ないように思います。そこでこのページでは、弊所が実際に特定建設業許可を取得した実績や経験をもとに、特定建設業許可の要件・手続き・成功事例などをわかりやすく、まとめました。
「特定建設業許可」についてあまり詳しくない方は、「第1章 特定建設業許可とは?」をお読みください。特定建設業許可について、わかりやすく説明しています。
実際に「特定建設業許可を取得する必要がある」という方は、より実践的な記載のある「第2章 特定建設業許可を取るための特殊な許可要件」「第3章 特定建設業許可を取るために必要な手続」についてお読みください。御社が具体的にどのような要件を満たし、どのような手続を踏めば特定建設業許可が取れるのか?ご理解いただけると思います。
「この際だから、許可取得手続きをお任せしたい!」という方は、「第4章 特定建設業許可の取得を行政書士法人スマートサイドに依頼したい方」以降をお読みください。面談の際にお聞きしたいことや用意していただきたい書類、特定建設業許可を取得するのに必要な費用・期間を記載しました。
「特定建設業許可とは、いったい何?」なのでしょうか?建設業許可は2種類あるのでしょうか?知事許可・大臣許可とは、何が違うのでしょうか?この章では、特定建設業許可の基本的なことについて、以下の3つを解説していきます。
| 1 | そもそも「建設業の許可」とは? | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 「般特新規申請」とは? | ||
| 3 | 特定建設業許可が必要な場合の具体例 | ||
分かっている方は分かっていると思うのですが、「建設業の許可」と言っても色々な許可の種類があります。ここでは、「特定建設業許可」は、色々な種類がある建設業許可のうちの1つであるということを説明します。
(1)一般的に言われている「建設業許可」とは?
よくお客様からご依頼を受ける「建設業の許可を取りたい」といった場合の、『建設業の許可』とは、『一般建設業許可』を指しています。通常、単に『建設業許可』という場合、この『一般建設業許可』を言います。この『一般建設業許可』がないと、500万円以上の工事(建築一式工事では1500万円以上の工事)を請け負うことができません。建設業者は、500万円以上の工事を請け負えるようするために、まずは、『建設業の許可』=『一般建設業許可』を取得しようとするわけですね。
ちょっと大きい工事になると、請負金額は簡単に500万円を超えてしまう。だから、どの建設業者さまも『建設業の許可』=「一般建設業許可」を取得するのに必死なわけです。
(2)では「特定建設業許可」とは?
工事の請負金額の観点から、上記の「一般建設業許可」と対比されるのが「特定建設業許可」です。500万円以上の工事をするには、一般建設業許可(単に「建設業許可」)が必要でした。これに対して、特定建設業許可は、
- 元請の立場で
- 工事の全部または一部を下請に出す場合
- その金額が5000万円(建築一式の場合は8000万円)以上になる
ときに必要になるのが、『特定建設業許可』です。難しいですね。1つ1つの要件を細かく見ていきます。
【元請の立場で】
特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負う「元請」の建設業者のみです。下請の仕事しかやらないといった建設業者の場合、「元請」になることがないのであれば、特定建設業許可は必要ないことになります。
【工事の一部を下請に出す場合】
特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接受けた工事の一部を下請に出す場合です。仮に元請の立場であったとしても「工事を下請に出さない」場合には、特定建設業許可を取得する必要はありません。現実的には、あまり考えられませんが、発注者からの仕事をすべて自社が元請として施工するような場合です。
【その金額が5000万円(建築一式の場合は8000万円)以上になる】
元請の立場で工事の全部または一部を下請に出す場合でも、その下請に出す際の金額が5000万円未満の場合には、特定建設業許可を取る必要はありません。あくまでも、元請の立場で、下請に工事を依頼する際の金額が5000万円以上になるときに必要になるのが『特定建設業許可』ということになります。
(3)「知事許可・大臣許可」とは何が違うのか?
一番初めに、「建設業の許可と言っても色々な許可の種類があります。」と書きました。そして、一般建設業許可と特定建設業許可の分類は、請負金額の観点からの分類でした。それでは、「知事許可」「大臣許可」とはどう違うのでしょうか?「知事許可」「大臣許可」も請負金額の大きさによる分類ではないのでしょうか?
「知事許可」「大臣許可」も、建設業許可の種類であることに間違いありませんが、「一般建設業許可」「特定建設業許可」のような金額という視点からの分類ではなく、『営業所がどこにあるのか?』といった視点から分類になります。
- 知事許可・・・営業所が1つの都道府県内にある建設業者
- 大臣許可・・・営業所が複数の都道府県にまたがる建設業者
ということになります。
では手引きにも書いてある「般・特新規」または、「般特新規申請」とは、何なのでしょうか?通常、建設業者さまが建設業の許可を取得する際には、「一般建設業許可」を取得するのが一般的です。技術者の資格や会社の財務内容などの許可要件が厳しい「特定建設業許可」をいきなり取得しようとする事業者さまは、特殊な事情がない限りいません。
とすると、どの事業者もまずは、「一般建設業許可」を取得したうえで、次の段階へのステップアップとして「特定建設業許可」を取得しようとするわけです。このステップアップの際に、『一般許可を特定許可に変える』申請のことを「般・特」新規と言います。この『一般を特定に変える』申請は、変更申請や更新申請ではなく『新規申請』扱いになります。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とでは、要件や手続きに様々な違いがあるので、「特定建設業許可の要件を備えているか?」といった新たな審査を時間をかけて行う必要があります。現在持っている「一般建設業許可」を「特定建設業許可」に変える申請は、『変更申請』ではなく『新規申請』になるのです。
どういった場合に、特定建設業許可が必要になるのか、もう少し具体的に見ていきたいと思います。前述のように、特定建設業許可が必要になるのは、
- 元請の立場で
- 工事の全部または一部を下請に出す場合
- その金額が5000万円(建築一式の場合は8000万円)以上になる
場合でした。以下の事例で、特定建設業許可が必要になるか皆さんも一緒に考えてみてください。
元請業者Aから工事の依頼を受けた一次下請業者Bが、6000万円の管工事を二次下請業者Cに発注する場合。Bは特定建設業許可が必要ですか?
(事例1の答え)この場合のBは、一次下請業者であって、元請業者ではありません。特定建設業許可が必要なのは「元請の立場として・・・」でした。ですので、仮に5000万円以上の金額の工事を下請に発注したとしても、Bは元請の立場にないので、特定建設業許可は必要ありません。
元請業者Dが、2億円の防水工事を受注しました。そのうち、一次下請業者Eに3000万円で、下請工事を発注しました。この場合の、Dは、特定建設業許可が必要ですか?
(事例2の答え)この場合のDは、確かに元請の立場にあるといえます。ですが、下請金額は3000万円であり、特定建設業許可が必要な5000万円以上の工事を下請に発注しているわけではありません。よって、Dは特定建設業許可は必要ありません。
元請業者Gは、一次下請業者であるH・Iにそれぞれ3500万円ずつの内装工事を依頼しました。この場合のGは、特定建設業許可が必要ですか?
(事例3の答え)Gは元請という立場にあることに間違いはありません。そしてH・Iにそれぞれ下請工事を発注しているので、特定建設業許可が必要になりそうです。もっともHに3500万円、Iに3500万円の工事を発注しており、特定建設業許可が必要な「5000万円以上」にあたるのでしょうか?この事例のように、複数の下請業者に工事を発注する場合は、『その合計額が5000万円以上か否か』によって、特定建設業許可が必要か否かを判断します。この事例では、合計額は7000万円(3500万円+3500万円)となり、5000万円を超えることになります。よって、この場合Gは特定建設業許可が必要になります。
さて、御社で実際に「特定建設業許可」が必要になったとして、御社は「特定建設業許可」の要件を満たしているのか?一番気になるところですね。特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可を取得するときとは違った、厳しい許可要件が課されています。
| 1 | 特定建設業許可の要件が厳しい理由 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 特定建設業許可の技術者要件 | ||
| 3 | 特定建設業許可の財産的要件 | ||
| 4 | 特定建設業許可のその他の要件 | ||
この章では、上記の4つの点に触れていきたいと思います。ぜひ、御社が許可要件をみたしているのか吟味しながら読んでみてください。
具体的な許可要件に入っていく前に、なぜ、特定建設業許可は一般建設業許可と比べて許可要件が厳しいのでしょうか?
そもそも特定建設業許可は、「元請の立場で」「工事の全部または一部を下請に出す場合」「その金額が5000万円(建築一式の場合は8000万円)以上になる」場合に必要でした。元請である以上、その工事を完成させるにあたって相当高度の技術力や経験が必要になります。ときには、総合的な観点から下請業者を指揮監督するようなことも必要になるでしょう。また、5000万円以上の金額の工事を下請に出すのですから、元請が倒産や財務危機に陥っては下請会社に迷惑が掛かってしまいます。支払いが遅れたり、支払いができなくなっては、下請会社に莫大な損害を与えることになりかねません。
このようなリスクを回避する観点から、特定建設業許可を取得しようという会社には、「技術者要件」と「財産的要件」の2つの側面で、一般建設業許可と比べるとかなり厳しい許可要件が課されています。
まずは、特定建設業許可に必要な技術者の要件から見ていきます。
(1)必要な資格
特定建設業許可を取得するのに必要な専任技術者の資格は以下の通りです。一般建設業許可では認められていた資格が、特定建設業許可の取得の際には認められていないことがありますので、注意して確認してください。
- 一級建設機械施工技士
- 一級土木施工管理技士
- 一級建築施工管理技士
- 一級電気工事施工管理技士
- 一級管工事施工管理技士
- 一級造園施工管理技士
- 一級建築士
- 建設総合技術監理
- 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
- 農業「農業土木」総合技術監理
- 電気電子総合技術監理
- 機械総合技術監理
- 機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理
- 上下水道総合技術監理
- 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理
- 水産「水産土木」総合技術監理
- 森林「林業」総合技術監理
- 森林「森林土木」総合技術監理
- 衛生工学総合技術監理
- 衛生工学「水質管理」総合技術監理
- 衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理
- 基礎施工士
ご覧の通り、一般建設業許可では認められていた「二級~」の資格が、特定建設業許可では認められていません。このため、社内に二級の資格者しかいない場合は、一級の資格を取っていただくか、もしくは、一級の資格者を採用していただいて、特定建設業許可を取得することになるかもしれません。
(2)必要な実務経験
資格を持っていない人を専任技術者として、一般建設業許可を取得する際には、その専任技術者に3年・5年・10年の実務経験が必要でした。特定建設業許可を取得するには、その実務経験に加えて、「元請として、消費税を含み4500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験」が必要になります。
指導監督的な実務経験とは、「建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督のような資格で工事の技術者を総合的に指導監督した経験」をいいます。一読してわかるように、このような経験を積んでいる人は、あまり多くないのではないのでしょうか?
(3)国土交通大臣の認定
(1)(2)に加えて、国土交通大臣が「(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者」は、特定建設業許可を取得する際の専任技術者の要件を満たします。
(4)指定建設業について
なお、「土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業」の7つの業種(「指定建設業」という)については、(1)または(3)に該当しなければならず、(2)の実務経験の証明を使って、特定建設業許可を受ける際の専任技術者になることはできません。
(5)実際に特定建設業許可を取得するには?
以上、特定建設業許可の取得に必要な「技術者の要件」を見てきました。かなり細かいところまで記載しましたが、実際の実務では、ほとんどが(1)に記載したの資格を利用して、特定建設業許可を取得しています。(1)の資格以外で、専任技術者の要件を満たして特定建設業許可を取得しようとする事業者さまも、いるにはいますが、私の知る限り「少数派」といってよいかもしれません。もし、どうしても特定建設業許可を取得したいというのであれば、
- 一級の資格者を採用していただく
- 一級の資格を社員に取得させる
ことをお勧めいたします。
次に財産的要件です。財産的要件について、言葉で説明するのはなかなか難しいものがあります。なぜなら、御社の財務諸表を実際に拝見して確認するのが一番早いからです。とはいうものの、手引きの記載を紐解くと、下記のようになりますので、まずは、自社で確認をしてみてください。以下の(1)から(4)までのすべての要件を満たしている必要があります。
(1)欠損比率
繰越利益剰余金の負の額から、資本剰余金・利益準備金・その他利益剰余金の合計額を引いてください。引いた額を資本金で割った結果が、20%以下であれば、(1)欠損比率の要件を満たします。もっとも、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計が、繰越利益剰余金の負の額を上回っている場合には、要件を満たしているので、上記の計算式を使う必要はありません。
(2)流動比率
流動資産合計を流動負債合計で割った結果が75%以上であれば(2)流動比率の要件を満たします。
(3)資本金
資本金は、2000万円以上であることが必要です。ピッタリ2000万円でも構いません。資本金が2000万円に満たないという事業者さまは、後ほど説明する「資本金の変更手続き」が別途必要になります。
(4)自己資本
純資産合計が4000万円以上であることが必要です。
(5)上記の財産要件を決算変更届で証明
「第3章 必要な手続」で記載しますが、般特新規申請は、決算変更届を提出した後に申請します。決算変更届を提出し、直前決算で(1)~(4)の財産的要件を満たしていなければ、般特新規申請を受理してくれることはありません。①直前決算の決算書類で(1)~(4)の財産的要件を満たしていることを確認し、②都庁に決算変更届を提出して、③般特新規申請をすることができるのです。
なお、直前決算期の財務諸表で(1)~(4)を満たしていない場合、
- 来期の決算期(1年後)まで待ったうえで、般特新規申請をする
- 財産的要件を満たすようにしたうえで、決算月を変更して、1年を待たずして、般特新規申請をする
という2つの方法が考えられます。
申請に当たっては、その他の要件である『一般建設業許可の取得時に苦労した「経営業務管理責任者」の要件』や『パソコンや事務用の備品がそろっているかといった「事務所」の要件』も重要です。しかし、般特新規申請をするということは、通常、一般建設業許可の要件は満たしているはずです。だからこそ、今持っている一般建設業許可を特定建設業許可に変更したいという理屈が成り立つわけです。
一般建設業許可の要件を満たしているということは、特定建設業許可を取得する際に特殊な「技術者の要件」や「財産的要件」以外の「経営業務管理責任者の要件」や「事務所要件」などはすべて満たしているはずです。ですので、般特新規申請の場合には、「技術者の要件」「財産的要件」を重点的にチェックすれば足り、それ以外の要件については、あまり神経質になる必要はありません。
「第2章 特定建設業許可を取るための特殊な要件」で確認した要件を満たしているとして、実際に特定建設業許可を取るためには、どのような手続きを踏んでいく必要があるのでしょうか?このあたりの手続きについては、はっきり言って行政書士の能力によって大いに差がつきます。「行政書士の腕の見せ所」といってもよいでしょう。特定建設業許可の意味や、許可要件について、いくら頭で理解していたとしても、実際にやってみたことがなければ、スムーズに申請までこぎつけるのは至難の業です。
もし、下記をお読みになって、「ちょっと難しいな」「わからないな」と思うようなことがあれば、迷わず、『実績のある行政書士』に相談することをお勧めいたします。
| 1 | 資本金の変更 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 専任技術者の変更 | ||
| 3 | 決算変更届の提出 | ||
| 4 | 般特新規申請 | ||
「1 資本金の変更」「2 専任技術者の変更」については、必ず必要というわけではありません。「場合によっては必要になる」という感じです。一方で「3 決算変更届の提出」「4 般特新規申請」については、必ず必要になります。
「第2章 特定建設業許可を取るための特殊な要件」の「3 財産的要件(3)資本金」の箇所でも触れたように、特定建設業許可を取得するためには、資本金が2000万円以上なければなりません。資本金が2000万円以上ない場合は、増資をして資本金を2000万円以上に増やすことが必要です。また、増資をして資本金が2000万円以上になって、登記簿謄本の「資本金の額」の変更が完了したら、別途、東京都庁の建設業課に資本金変更届を提出しなければなりません。
このように、資本金の変更が必要になる場合には、①登記簿謄本の変更のみならず、②資本金変更届の提出を経てからでないと、般特新規申請に進めませんのでご注意ください。具体的には、以下のような流れになります。
まず、資本金を変更するには、株主総会が必要です。株主総会議事録を作成して、株式会社変更登記申請の際に、添付書類として付ける必要があります。資本金は、株式会社の登記事項です。資本金を変更(増資)した場合には、法務局へ株式会社変更登記申請をしなければなりません。この点については、司法書士の専属業務になりますので、手続きを専門家に外注する場合には、司法書士の先生に依頼するようにしましょう。
次に、「株主総会を開いて、登記を変更して、おしまい!?」では、ありません。資本金変更後の新しい登記事項証明書が出来上がったら、資本金の変更から30日以内に、東京都庁の建設業課に資本金変更届を提出する必要があります。
「第2章 特定建設業許可を取るための特殊な要件」の「2 技術者要件」の箇所でも触れたように、特定建設業許可を取得するためには、一級の資格者が必要になります。
そのため、二級の資格者を専任技術者として一般建設業許可を取得した建設業者に関しては、専任技術者変更届を提出し、一級の資格者を専任技術者にしてからでないと、般特新規申請をすることはできません。なお、専任技術者は役員である必要はないので、登記簿謄本の変更は必要ありません。
例えば、管工事の建設業許可を取得する際に、「二級管工事施工管理技士」を専任技術者として一般建設業許可を取得した場合。この会社が特定建設業許可を取得するには、専任技術者を「二級管工事施工管理技士」から「一級管工事施工管理技士」に変更する必要があります。なぜなら、「二級管工事施工管理技士」では、特定建設業許可取得に必要な技術者の要件を満たしていないからです。
また、同じように、たとえば、建築一式の建設業許可を取得する際に、「二級建築施工管理技士(建築)」を専任技術者として一般建設業許可を取得した場合。この会社が特定建設業許可を取得するには、専任技術者を「二級建築施工管理技士(建築)」から「一級建築施工施工管理技士」または、「一級建築士」に変更する必要があります。
「一般建設業許可」を「特定建設業許可」に変更する『般特新規申請』をする場合、その前提として必ず直前決算期の決算変更届を提出していなければなりません。なぜでしょうか?「第2章 特定建設業許可を取るための特殊な要件」の「3財産的要件」でも書いたように、特定建設業許可を取得するためには、①欠損比率、②流動比率、③資本金額、④自己資本の4要件を満たしていなければなりません。この4要件を満たしているか否かを確認するために、直前決算期の決算変更届を提出する必要があるわけです。
あくまでも東京都の取り扱いですが、通常は、決算変更届を2番窓口に提出し、後日、般特新規申請を1番窓口に提出します。ただし、同時に両方提出する場合は、決算変更届も般特新規申請も1番窓口に提出するようです。
特定建設業許可を取るために必要な手続の最後は、『般特新規申請』です。前にも書きましたが、「一般建設業許可」を「特定建設業許可」に変える申請のことを『般特新規申請』と言います。『変更』扱いではなく、『新規申請』扱いになります。
新規申請という扱いなので申請書類としては、下記のものが必ず必要になります。
- 建設業許可申請書
- 役員などの一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 定款
- 財務諸表
- 営業の沿革
- 健康保険などの加入状況
- 主要取引金融機関名
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 許可申請者の住所、生年月日などに関する調書
- 株主(出資者)調書
- 登記事項証明書
- 納税証明書
確認資料を除いた申請書類だけでも、こんなにあるのですから、とても多いですね。

ご依頼頂いた時のお客様の状況は、下記の通りです。
| ご依頼時のお客さまの状況 | |
|---|---|
| 許可状況 | 東京都一般建設業許可(建築一式) |
| 技術者資格 | 2級建築施工管理技士(建築) |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 純資産合計 | 4,000万円未満 |
| 決算期 | 5月末 |

この時点で、通常であれば、「翌年5月末を待ち、それまでに資本金を2000万円にしたうえで、純資産を4000万円以上にし、般特新規申請をしましょう」となります。ところが、この会社の場合、翌年1月には、特定建設業許可を持っていなければならない事情がありました。5月まで待てません。
そこで、
- (1) 早急に資本金を1500万円から2000万円に増資し
- (2) そのうえで、決算月を5月から9月に変更し
- (3) (1)(2)と同時進行で技術者を二級から一級に変更して
- (4) 今年11月に「決算変更届」と「般特新規申請」を同時提出
するという方法をご提案いたしました。
以下では、この案件で実際に行った具体的な手続の流れを記載します。ちょっと細かいかもしれません。また、司法書士の先生や、税理士の先生の協力も必要になってきます。
(1)手続1:1500万円から2000万円への増資
ご依頼時の資本金が1500万円(2000万円以下)であったため、特定建設業許可を取得するにあたって、500万円の増資が必要になります。資本金の額は、登記記載事項であるため、資本金の額の変更には登記変更申請書を法務局に提出しなければなりません。登記変更申請書の作成は、司法書士の専属業務で行政書士が行うことはできません。この点については、弊所と提携している司法書士の先生をご紹介し、連携しました。また、資本金を500万円増資した結果、純資産が4000万円以上になることも確認をしました。
![]()
(2)手続2:東京都庁へ資本金変更届の提出
資本金を変更した場合には、変更から30日以内に、東京都庁へ資本金の変更届を登記簿謄本と一緒に提出しなければなりません。司法書士の先生から登記簿謄本の変更が完了した旨の報告を受けてから、都庁建設業課に資本金変更届の提出に行きました。
![]()
(3)手続き3:決算月の変更
直前決算(今年5月)では、財産的要件を満たしていなかったので、本来であれば、次期決算(翌年5月)まで待つところですが、今回はそれができません。そこで、資本金の変更を経て、財産的要件を満たした時点で、決算月を9月に変更しました。決算月の変更に関しては、顧問税理士の先生にお任せしました。
![]()
(4)手続4:技術者の変更
上記の財産的要件の準備と同時並行で、技術者の要件についても準備しなければなりません。この会社には、常勤の一級建築施工管理技士の方がいらっしゃったので、「二級建築施工管理技士から一級建築施工管理技士への専任技術者変更届」を東京都庁に提出しました。
![]()
(5)手続5:決算変更届の提出
資本金を変更し財産的要件を満たし、決算期を変更し新たな決算期を迎えてから、決算変更届を提出いたしました。ちょっとややこしいですね。時系列で書くと以下のようになります。
『今年5月決算の時点では、特定建設業許可に必要な財産的要件を具備していなかった』
↓
『資本金を変更し、特定建設業許可に必要な財産的要件を備えた』
↓
「次回の決算(翌年5月)まで待てないので、決算月を9月に変更した』
↓
『今年9月末決算では、特定建設業許可に必要な財産的要件を備えているので、今年9月末時点の決算変更届を東京都庁に今年11月に提出した』
という流れになります。
![]()
(6)手続6:般特新規申請の提出
実際には、決算変更届と般特新規申請を同時に提出しましたが、ここでは、便宜上分けて記載します。都庁の審査担当者は、①直前決算期(今年9月)の決算変更届で、特定建設業許可に必要な財産的要件を具備しているか確認し、②般特新規申請書類で技術者が特定建設業許可に必要な要件を具備しているか確認します。
![]()
(7)無事、工事の期日までに、特定建設業許可取得!
般特新規申請をしたのが今年11月でしたが、無事年内に特定建設業許可を取得することができました。「翌年1月にある工事までに、特定建設業許可を取得したい」というお客様からのご依頼に無事、お応えすることができました。
「特定建設業許可を取得するのは難しい」「知識のある専門家に依頼した方が安心できそうだ」ということは、わかっていただけたと思います。もちろん「自社で処理する」「付き合いのある行政書士にお願いする」ということでも構いませんが、御社が行政書士法人スマートサイドに依頼をしていただく際には、下記のような流れになりますので、参考になさってください。
| 1 | 特定建設業許可取得のための手続きの流れ | ||
|---|---|---|---|
| 2 | お問い合わせ・面談の際にお聞きしたいこと | ||
| 3 | お客さまにご用意して頂きたい書類 | ||
弊所に特定建設業許可取得のための手続きをご依頼頂いた際の手続きの流れを簡単にご説明させて頂きます。
| 【1】 | メールフォームからのご連絡
まずは、「特定建設業許可を取得したい」旨、メールフォームからメールにてご連絡下さい。電話による相談・手続きに関する質問は、承っておりません。打合せ日時を調整のうえ、メールにて返信させて頂きます。 |
|---|
![]()
| 【2】 | 相談料のお振込み
打合せ日時が確定次第、相談料(1時間/11,000円)をご請求させて頂きます。相談日前日までに、指定の口座にお振込みをお願いします。その後、打合せを実施させて頂きます。なお、弊所では、一人一人のお客様に対する適切な対応および質の高い打合せ時間確保の見地から、無料での相談は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。 |
|---|
![]()
| 【3】 | 打ち合わせの実施
特定建設業許可に必要な要件、資料、期間、費用などをご案内させて頂きます。とくに「急ぎ案件」の場合、特定建設業許可の要件を満たしているか否かの精査が必要です。なお、特定建設業許可取得にかかる費用は、ホームページに公表している通りですが、事前に「お見積り」もご提示させて頂きます。 |
|---|
![]()
| 【4】 | 正式なお申込み+手続きの開始
打合せ実施後、お見積にご納得いただいたうえで、正式に手続きを依頼したい方は、その旨、お申込みください。正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。御社からのお振込みの確認が取れ次第、特定建設業許可取得に向けた準備を開始させて頂きます。 |
|---|
![]()
| 【5】 | 申請および許可通知書の受領
履歴事項全部証明書や取締役の身分証明書などの公的書類は、すべて、弊所にて代理取得いたします。申請書類の完成まで、2週間程度の時間がかかります。ご依頼を頂いてからひと月程度で、都庁に申請を行います。申請完了後ひと月程度で、御社に特定建設業許可の許可通知書が届くことになります。 |
|---|
Q1:東京都での一般建設業許可を持っていらっしゃいますか?
Q2:一般建設業許可を取得した際の副本はお持ちですか?
Q3:一級の国家資格者は、常勤で勤務されていますか?
Q4:決算変更届の提出など必要な申請は、滞りなくすませていますか?
以下は、「特定建設業許可を取得したい」と考えているお客様にご用意していただきたい書類の一部です。いずれも、打ち合わせの際に、ご用意いただくと、特定建設業許可取得の可否の判断をスムーズに行うことができ、許可取得までの時間を短縮することができます。
(1)許可申請書類の副本一式
(2)直前決算期の決算報告書類一式
(3)資格者の一級国家資格合格証
(4)その他
実際に、行政書士法人スマートサイドに「特定建設業許可の取得の依頼」をされた場合に、許可取得までかかる費用や日数について、ご説明いたします。御社の予算や業務スケジュールの参考にしてみてください。急ぎ対応が必要な場合には、別途対応をさせて頂きますが、一般的には、下記のように「お問合せ~許可申請まで2週間程度」の期間をいただければと思っております。
(期間)
| スケジュール |
日数 |
|---|---|
| 問合せ~面談 | 0日~3日 |
| 面談~書類収集・書類作成 | 7日程度 |
| 必要書類の押印~申請 | 4日程度 |
| 合計 | お問合せ~許可申請まで2週間程度 |
(費用)
「申請の難易度」「決算変更届の提出や技術者の変更といった手続きの数」「急ぎか否か」などの事情によって、様々です。お打ち合わせの実施後、お見積りをご提示させていただきます。以下の費用は、弊所でご依頼を受けることが多い【決算変更届(1期分)の提出+特定建設業許可申請】といった最もシンプルなご依頼の場合です。
| 都に支払う費用 |
行政書士報酬 |
お支払い額合計 |
|
|---|---|---|---|
| 決算変更届の提出 | ー | 55,000円 | 55,000円 |
| 特定建設業許可申請 |
90,000円 |
330,000円 | 420,000円 |
- 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
- 特定建設業許可取得のために、「技術者の変更届」や「増資をした際の変更届」が必要になる場合があります。別途お見積りをご提示させていただきます。
- 住民票や納税証明書の取得費用(1通2200円)については、別途ご請求させていただきます。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。「特定建設業許可」について、理解は深まりましたか?「これなら自社でも特定建設業許可を取得できそうだ!」という具体的なイメージが湧いてきましたでしょうか?
- 特定建設業についてわかったような気がする
- 般特新規申請をするまでの手続きが理解できた
- 特定建設業許可の特殊な要件が分かりやすかった
など、御社のお役に立つことができたら光栄です。
そもそも、私が「特定建設業許可徹底解説」のページを書こうと思ったきっかけは、「特定建設業許可について、情報が少なすぎる」と感じたからです。インターネットを検索しても、専門の書籍を手にとっても、「特定建設業許可申請(般特新規申請)」に特化して書いてあるものは、ほぼありません。あったとしても、とても薄っぺらい情報ばかりのモノが多いです。
建設業許可専門の行政書士をやっていて、事業者さまから特定建設業許可の問い合わせを多く受けており、事業者さまが特定建設業許可の取得について困っているのにも関わらず、それに応えうるような情報源が少なすぎることに歯がゆさを感じたのが、「特定建設業許可徹底解説」のページを書こうと思ったきっかけです。
一方で、特定建設業許可について、実績のある行政書士が少ないのも、また事実です。特定建設業許可は、一般建設業許可に比べて取りたいと希望する事業者様は多くありません。その分、建設業専門をうたっている同業の行政書士事務所においても、実績を多く積んでいる事務所というのは、限られているのかもしれません。
その点、行政書士法人スマートサイドは、一般建設業許可はもちろんのこと、特定建設業許可についても、このページで記載したような様々な知識・経験・実績を備えています。また、確実に手続きを進めたいというご要望に応じて、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)を実施しています。「建設業許可の取得の状況」「特定建設業許可が必要な理由」「いつまでに必要か?というスケジュール」などを詳細にお聞きした上で、御社にとって最適な方法をご提案あせて頂くことが可能です。
特定建設業許可を取得したいという事業者さまからの、お問合せにはたくさんご対応させていただきました。中には、一人で抱えてしまい、ひどく疲れ切って弊所に相談に見えたお客様もいらっしゃいました。このページを見ていただいてわからない点や疑問に思った点がある方は、事前予約制の有料相談をお申込みください。御社の特定建設業許可取得の一助になれば幸いです。

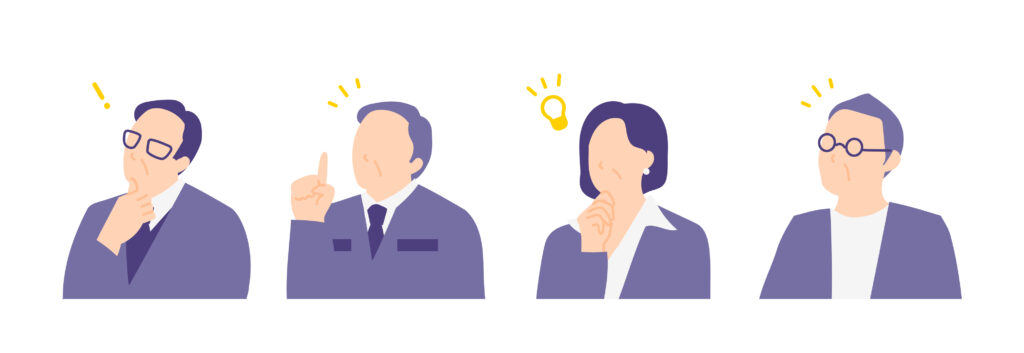

-scaled-e1738530668562-1024x328.jpg)