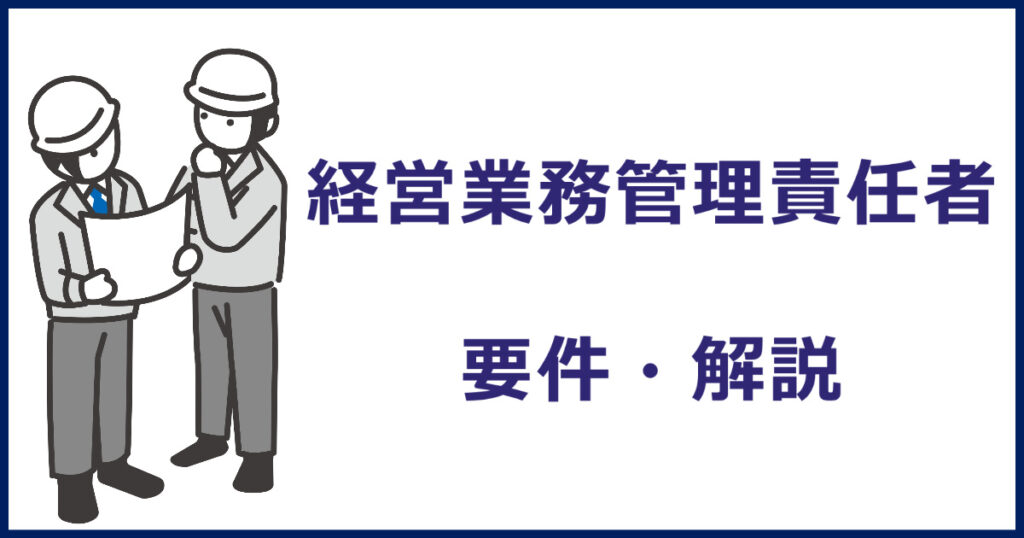
このページは、
✅ 経営業務管理責任者とは、どういった人のことを言うのか?
✅ うちの会社にそんな要件を満たす人がいるのだろうか?
✅ 経営業務管理責任者がいないと、絶対に許可が取れないのか?
✅ どうしても建設業許可が欲しい場合は、どうすればよいのか?
というような「経営業務管理責任者」の要件について、詳しく知りたい方のためにご用意いたしました。
中には、
- 「書類を作りさえすれば、なんとかなるでしょ」
- 「都庁に口頭で説明するから、大丈夫!」
- 「お金ならいくらでも払うので、なんとかしてください」
というようなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。残念ながら、そのような考えは通用しないのが現状です。これから東京都建設業許可を取得しようと考えている事業者さまは、もちろんのこと、「何とか建設業許可を維持したい…」とお考えの事業者さまも、ぜひ、経営業務管理責任者の要件について理解を深めて、今後の会社運営に役立ててもらいたいと思っています。
建設業許可を取得したいと検討中の人の中には、「建設業の許可を取るには『経営業務管理責任者』が必要らしい。だけど、いったいどんな条件が必要で、何を準備すればよいのか?まったくわからない」といったように、「経営業務管理責任者」といった言葉を初めて聞く方も多いのではないでしょうか。
経営業務管理責任者が必要なのはわかったけど、実際には『どうやって、それを証明するの』という疑問も生じてきます。証明がうまく行けば、許可取得に近づくわけですから、経営業務管理責任者の証明はとても重要です。
このページでは、【1】で経営業務管理責任者の実体的な要件を解説します。【2】では、その要件をどのような書類で証明していくのか?について解説していきます。さらに【3】では実際の許可事例を参考にします。実際の事例を見ることによって、御社が今後どのように経営業務管理責任者の要件を満たしていけばよいのかを検討してみてください。
【4】では、一度取得した建設業許可を維持するための注意点についても言及していきます。せっかく建設業許可を取ったのだから、長い間、その許可を維持したいですね。許可を失えば、500万円以下の工事しかできなくなるので、許可を維持したいのは当たり前です。ところが、不慮の出来事や、経営業務管理責任者の退社などが原因で、建設業許可を維持できず「廃業」せざるを得ない事業者さまが多数存在します。
【5】と【6】では、実際に行政書士法人スマートサイドが、建設業許可取得の専門家として提供するサービスの内容にも触れていますので、よく読んだけどわからないという人は、ぜひ、事前予約制の有料相談をお申込みください。
経営業務管理責任者という要件は、建設業許可を取得する上では、とても重要な要件ですが、普通に生活をしていて、そんな言葉は「聞いたことがない」人がほとんどだと思います。しかし、建設業許可を取得するうえで、絶対に欠かすことができない、とても重要な要件です。この要件を理解することが「建設業許可取得のすべての始まり」だと思ってください。『この要件を満たしていることをどう証明していくか』が建設業許可取得のためのとても大きなポイントになってきます。
特に「東京都」に関しては、この要件についての審査が他県に比べて厳格です。東京都で建設業許可を取得したいとお考えの方は、必ず理解しておいてほしいところです。
経営業務管理責任者の意味・経験・常勤性・地位
(1)経営業務管理責任者の意味
「経営業務管理責任者」とは、『営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する権限を有する者』をいいます。簡単に言うと、「社内的にも社外的にも、建設業を行う上で、責任者としての立場にいる人」と言い換えられます。もっと簡単にイメージすると、『経営』『業務』『管理』『責任者』の文字通り、「建設業の経営と業務について、管理者たる地位を有し、責任ある立場の人」といったくらいの理解で良いでしょう。むしろ重要なのは以下の(2)(3)(4)です。
(2)5年以上の取締役・個人事業主としての経験
建設業許可を取得するために「経営業務管理責任者」となるには、建設業に関して、5年以上の『取締役』もしくは『個人事業主』としての経験が必要です。この『5年以上の取締役・個人事業主としての経験』がとても重要です。例えば、「飲食店で個人事業主の経験があります」とか「アパレル関係の会社で取締役をやっていました」とかでは『建設業の許可を取得するうえでの必要な経験』に含まれません。
御社が「内装工事」の許可を取得したいのであれば、『建設業の個人事業主としての経験が5年以上』もしくは『建設業を行っていた会社の取締役としての期間が5年以上』なければなりません。残念ながら、ほとんどの事業者様がこの部分で躓きます。「会社員・従業員」の経験はあっても「個人事業主」「取締役」の経験を有している人は、そう多くないからです。
(3)常勤性
経営業務管理責任者は、御社に常勤している必要があります。常勤とは『一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事していること』をいいます。一般的には、9時~18時の間、勤務していることを言います。
経営業務管理責任者の要件に常勤性が求められる理由は以下の通りです。『「経営業務管理責任者」は、『社内的にも社外的にも、建設業を行う上で、責任者としての立場にいる人』でした。そのような人が、「御社に常勤していない」もしくは「他社に常勤している」というのはありえないから』というものです。この常勤性については、のちのち問題になってきますので、経営業務管理責任者は、申請会社(建設業許可業者)に常勤していなければならないと、必ず覚えておいてください。
(4)取締役としての地位
経営業務管理責任者は、御社の取締役であることが必要です。先ほども述べましたが、経営業務管理責任者は、御社の建設業に関する責任者的立場にある人ですから、御社の取締役としての地位を有していることが求められます。社会通念上、ただの平社員では「責任ある立場にある人」とは言い難いです。もし現時点で、御社の取締役の中に経営業務管理責任者の要件を満たす人がいなかった場合には、要件を満たす人を探してきて、御社の取締役になってもれば、建設業許可の要件を満たすことになります。
経営業務管理責任者の具体例
では、具体的に「どういった人たち」に「どういった経験」があれば、経営業務管理責任者に該当するのでしょうか?
(1)個人事業主として5年の経験
会社(法人)の取締役としての経験がなくても、個人事業主として5年以上の経験があれば、経営業務管理責任者になることはできます。例えば、「会社を退職し、その後、個人事業主として管工事を5年以上やっています」という場合などが、該当します。
(2)個人事業主として3年・会社の取締役として2年の経験
個人事業主としての期間と、会社の取締役になってからの期間を合算することは可能です。会社設立(法人成り)した事業者さまに多い事例です。例えば、「大工工事の個人事業主をやっていましたが、売り上げが大きくなってきたので、2年前に法人成りして、代表取締役に就任しました」といった場合です。会社設立後、2年しか経過していませんが、個人事業主時代の経験が3年以上あれば、足して5年になりますので、経営業務管理責任者の要件を満たすことになります。
(3)自社の取締役として5年の経験
自社で取締役を5年以上やっていれば、経営業務管理責任者の要件を満たします。一番シンプルなパターンです。このパターンで建設業許可を取得するケースが一番多い印象です。例えば「自分で会社を立ち上げて5年以上経ちます」「その間ずっと、とび・土工・コンクリート工事をやってきました」という場合です。
(4)他社の取締役として4年・自社の取締役として1年の経験
取締役の経験は、自社ではなく、他社での経験でもOKです。例えば「おなじグループ会社が建設業をやっていました。その会社で4年間取締役の経験があります。その後、今の会社の取締役に就任し1年が経ちました」といったケースです。前の会社での取締役の期間と今の会社での取締役の期間を合算すれば、5年以上になります。そのため、経営業務管理責任者の要件を満たします。
(5)他社の取締役として5年の経験
現時点で自社に経営業務管理責任者の要件を満たす人が、全くいないとしても、他社で5年以上、取締役をやっていた人を自社に招聘するという方法があります。「自社で要件を満たさない以上、要件を満たす人を連れてくる」というイメージです。例えば、「他社を引退した方を、自社の取締役に招聘する」または、「要件を満たす人を知合いから紹介してもらい、取締役になっていただく」という方法です。レアケースのように見えるかもしれませんが、この方法で建設業許可を取得する事業者さまは結構多いです。
取締役・個人事業主としての経験がない場合
では、取締役としての5年の経験も、個人事業主としての5年の経験もない場合、建設業の許可を取得することはできないのでしょうか?経営業務管理責任者の要件に関する問い合わせの中で、1番多いのがこの質問です。この点について、緩やかながら、経営業務管理責任者の要件を緩和する方向に動いています。
執行役員としての経験や地位
仮に取締役もしくは個人事業主としての経験がない場合でも「執行役員としての経験や地位」がある場合には、経営業務管理責任者になることができます。「取締役」と「執行役員」との一番大きな違いは、登記簿謄本上に登記されるか否かという点にあります。「取締役」は登記の対象ですが「執行役員」は登記の対象ではありません。
「執行役員」は登記の対象ではないため、経営業務管理責任者になるには、通常よりも、多くの書類を準備しなければなりません。「組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」「執行役員規定」など、さまざまな書類が必要になりますが、執行役員としての経験や地位があれば、仮に、取締役としての経験がなくても経営業務管理責任者の要件を満たすことがあることを、ぜひ覚えておいてください。
人材紹介会社の紹介を受けてみては?
これはあくまでも個人的な見解ですが、『「人材紹介会社」などを利用して要件を満たしている人を紹介してもらう』という方法を取ることも、建設業許可取得の可能性を高めるための手段ということができると思います。弊所でも実際に、そのような手段をとって、経営業務管理責任者を招聘し、建設業許可を取得することができた人が、何社もいらっしゃいます。「大手の人材派遣・紹介会社からの紹介を受けて、建設業許可を取得した」という事業者さまは多くいらっしゃるのが事実です。要件を満たしていれば、余計な資料を提示することもなく、すんなりと許可取得に至るはずです。
どうしても建設業許可を取得しなければならないという方は、一度、人材派遣・紹介会社を利用することも検討してみてください。
経営業務管理責任者の意味が理解できたでしょうか?経営業務管理責任者の意味について理解できたら、次は、「経営業務管理責任者の要件」を証明しなければなりません。行政書士として何件も建設業許可申請を行っていますが、この「証明」がとても大変です。この点に関しては、やはり素人である事業者さまご本人で準備をするよりも、専門家である行政書士に依頼することをお勧めいたします。ここでは、「現在の常勤性」を証明するものと「過去の経営経験」を証明するものの2つに分けて解説していきたいと思います。
現在の常勤性を証明する資料
前述の通り、経営業務管理責任者は、御社(許可を取りたい会社)に常勤していなければなりません。経営業務管理責任者は、「建設業に関して、対外的にも対内的にも責任者としての立場にある人」をいいます。その経営業務管理責任者が、「御社に常勤していない」とか「他社の常勤になっている」ということは常識としてあり得ないということは【1】でも記載しました。そこで、建設業許可を取得するためには、「経営業務管理責任者が今現在、御社に常勤していること」を証明しなければなりません。
住民票(※東京都では不要になりました)
かつて東京都の建設業許可を取得する際には、住民票の提出が求められていましたが、現在では住民票の提出は求められていません。しかし、「経営業務管理責任者の住所が、どこか?」という点は、とても重要です。なぜなら、「常勤」とは一般的に『9時から18時まで会社に勤務していること』をいいます。住民票上の住所が会社所在地からあまりにも距離がはなれている場合、「経営業務管理責任者が本当に御社に常勤しているのか」と疑義が生じてしまうからです。
常勤性がないにもかかわらず、毎日出勤しているかの如く装って常勤性を偽装することを、「名義貸し」と言います。名義貸しは、法律違反です。そのような違法な手段による建設業許可の取得を防ぐために、経営業務管理責任者がどこに住んでいるかは重要です。例えば、御社が東京都新宿区にあるのに、経営業務管理責任者の住民票が「宮城県仙台市」であった場合。ほんとうに毎日会社に出勤しているのか?常勤性に疑義が生じてきますね。
かつては、常勤性に疑義が生じた場合(住民票上の住所から勤務地までの通勤時間がおおむね2時間以上の場合)、毎日の通勤記録(ETCの明細、駐車場の賃貸借契約書や通勤定期券のコピー)を求めらることがありました。また、「社宅に住んでいる場合」のように現住所が住民票上の住所と異なる場合には、社宅の賃貸借契約書、電気・ガス・水道料金の領収書などの提示を求められることがありました。
現在では、そこまで厳しい運用はされていません。しかし、だからと言って経営業務管理責任者の住所がどこであってもよいわけではないことに注意が必要です。
健康保険被保険者証(事業所名の記載があること)
マイナ保険証の登場により、健康保険被保険者証の取扱いにも、だいぶ変更点があるようです。このあたりについては、手続に詳しい専門家でも、現時点での運用がどうなっているのか?という判断が難しい部分があります。
まず、健康保険被保険者証(事業所名が印字されているもの)のコピーは、常勤性の証明資料になります。1度、手元にある健康保険被保険者証を確認してみてください。御社の事業所名が記載されているでしょうか?健康保険は所属している会社を通じて加入し、毎月の給料から天引きされる形で保険料を納入していると思います。ですので、健康保険被保険者証に事業所名が記載されていれば、その会社に常勤しているという証明が成り立つわけです。
健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合
では、健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合はどうすればよいのでしょうか?この場合には、以下のような別途資料の提示が必要になります。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 厚生年金記録照会回答票
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
- 確定申告書
ちなみに、弊所では、「2.厚生年金記録照会回答票」を用いることが多いです。「厚生年金記録照会回答票」は本人から委任状をもらいさえすれば、年金事務所にて取得することができるので、とても便利です。また、「1」の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」をお客さまに提出してもらうこともあります。もっとも、75才以上の方は、社会保険に加入できませんので、「1」で対応することができません。そういった場合には「3」の「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し」で対応することもあります。
過去の経営経験を証明する資料
現在の常勤性の証明は、「健康保険被保険者証」+「厚生年金記録照会回答票」でうまく行く場合が多いです。ところが、「過去の経営経験の証明」は、なかなか一筋縄にはいきません。経営業務管理責任者に要求される「過去の経営経験」とは、『建設業に関する取締役もしくは個人事業主として5年以上の経験』です。それでは、どうやって、過去の経営経験を証明していけば良いのでしょうか?
経営業務管理責任者が法人の取締役であった場合
経営業務管理責任者が法人の取締役であった場合は、その取締役の期間(5年以上)を『登記簿謄本』で証明します。登記簿謄本は、法務局で誰でも取得することができます。仮に、会社が解散していた場合や取締役になった時期が古い場合には、閉鎖登記簿謄本や手書き(コンピュータ処理以前)の謄本を入手しなければなりません。地方法務局の支部に郵送請求するようなこともあります。
経営業務管理責任者が個人事業主であった場合
経営業務管理責任者が個人事業主であった場合は、確定申告書5期分が必要です。個人事業主にとって、確定申告は必須ですね。その確定申告書類によって、自身が個人事業主として5年以上、建設業を経営していたことを証明するわけです。
この確定申告書を「破棄してしまった」とか「なくしてしまった」という方がいらっしゃいます。そうなると東京都で建設業許可を取ることがかなり難しくなります。もっとも他県では建設業許可申請の際に、確定申告書を必要としていない県もあります。確定申告書をなくしてしまったという方は、「東京都ではなく他県でも」といった柔軟な考え方が必要になってきます。
業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳(5年分)
上記の登記簿謄本(法人の取締役の場合)・確定申告書(個人事業主の場合)に加えて、取締役であった5年間(もしくは個人事業主であった5年間)本当に建設業を経営していたことを証明するために『業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳』が必要です。前述したように、取締役の経験や個人事業主の経験は、建設業に関するものでなければなりません。そのため、ただ単に5年間の取締役(個人事業主)としての経験があるというだけでなく、建設業の取締役(もしくは個人事業主)としての5年以上の経験が求められているのです。
『業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳』の準備に皆さん苦労します。理由は以下の3点です。
- 請求書は「工事に関する請求であること」が明確に読み取れるものでなければなりません。たとえば、「修理」「保守・点検」「物販」などは工事として認められませんので注意しましょう。
- 求められる請求書と通帳は最低でも3か月に1件ペースです。証明期間は5年間なので、20件以上の請求書とそれに対する通帳の入金記録が必要になります。
- 請求金額に関しては、「500万円未満」であることが妥当でしょう。これから建設業許可を取得しようとしている会社に、過去の実績として500万円以上の工事があっては建設業法違反となってしまいます。
まずは「請求書+入金通帳(5年分)」の確認から
私がお客様によく言うことですが、「まずは3か月に1件ペースで5年分以上の請求書と入金通帳を準備できるか否か」から確認しましょう。確かに建設業許可を取得するには、他にもそろえなければならない書類がたくさんあります。しかし、東京都建設業許可で一番難しいのは、この「3か月に1件ペースで5年分の請求書と入金通帳」を用意できるか否かという部分です。
『時間を使って申請書を作成し、そのほかの証明書類を取得しました。けど、請求書と入金通帳を準備できませんでした。』これでは、必要書類の取得や申請書類作成にかけた時間は水の泡です。審査の際には、請求書の「工事件名」「工事内容」「請求内容」「請求日」、入金手帳の「入金日」「入金額」といった項目を、1件1件チェックされます。
先ほども書きましたが、例えば
- 保全、点検、修繕は工事にあたらないので、5年の期間に含まれません。
- 期間が空きすぎているので、もう何件か請求書を準備してください
など、細かい部分の指摘を受ける可能性があります。そのため、準備にも相当な労力と時間をかけなければなりません。まずは、請求書と通帳に問題がないことを確認してから、次のステップに進むことをお勧めいたします。
さて、「【1】経営業務管理責任者の要件」および「【2】経営業務管理責任者の要件の証明方法」を見てきましたが、建設業許可取得に向けた道筋が見えてきたのではないでしょうか?ここでは「【3】建設業許可を取ることができた事例・できなかった事例」と題して、実際に許可を取れた事例と残念ながら許可が取れなかった事例をご紹介します。御社の現在の状況とリンクさせながらお読みいただければと思います。御社の許可取得の参考にしてみてください。
東京都建設業許可を取ることができた事例
まずは、東京都で建設業許可を取得できた事例です。
電気工事業の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。経営業務管理責任者の要件を満たす人が社内にいなかったため、知り合いの方を中心に探していただきました。社長の親戚で、10年以上個人事業主として電気工事業を営んでいた方がいらっしゃったので、その方に経営業務管理責任者になっていただくことになりました。
- 個人事業主として10年以上電気工事業を営んでいたこと
- その間の確定申告書類や請求書+通帳を捨てずに取っていたこと
から、経営業務管理責任者としての要件を証明することができ、無事許可を取得するに至りました。
土木一式工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。社長自身が過去に静岡県で建設会社の取締役として5年以上の経験がある方でした。過去の取締役としての経験が平成初期であったため、静岡地方法務局・沼津支局に手書き(コンピューター処理以前)の登記簿謄本の取得を請求しました。また、その間の請求書+通帳は処分して、全く持っていないとのことだったので、建設業許可業者であったことを証明するため、静岡県に情報開示請求をしました。
「取り寄せた謄本から5年間役員であったこと」が認められ、また、情報開示した文書から「取締役であった5年間、静岡県知事許可業者であったこと」も認められ、経営業務管理責任者の要件をクリアしました。その結果、無事、東京都の建設業許可(土木一式工事)を取得することができました。
管工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。会社を設立して2年目でしたが、会社を設立する前に10年以上、個人事業主として管工事を営んでいる方でした。この事業者さまの場合、経理を担当している奥様が、過去の個人事業主時代の書類を含めて、すべて必要な書類をファイリングし、原本を保管していました。このようなケースでは、会社を設立して2年目ですが、個人事業主時代の経験も証明できるので許可取得の可能性が大変高くなります。
実際に、個人事業主時代3年分の確定申告書、法人成りしてからの登記簿謄本、通算5年分の請求書+通帳を提示して、無事許可を取得するに至りました。
建築一式工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。この事業者さまに工事の経験はありません。経営業務管理責任者の要件を満たす人も在籍していません。ではどうやって許可を取得したのでしょうか?
この会社の場合、人材紹介会社に間に入ってもらい、大手ゼネコンの取締役の経験のある方を取締役として招聘し、経営業務管理責任者の要件を満たしました。大手ゼネコンは、当然建設業許可を持っていましたし、その人が取締役であることも登記簿謄本を取得することによって確認することができます。このように、工事の経験や実績がまったくない会社であったとしても、要件を満たす人を取締役に招き入れることによって、東京都の建設業許可を取得することはできるのです。
東京都建設業許可を取ることができなかった事例
次は、残念ながら東京都建設業許可の取得に至らなかった事例です。
経営業務管理責任者の要件が緩和傾向にあるといっても、「5年が3年になる」とか、「取締役・個人事業主としての経験が不要になる」と考えるのは間違いです。一部そういった『提言』がなされているようですが、今のところ事実としてそこまでは進んでいません。
この事業者さまの場合、会社を設立して4年しか経っておらず5年の要件を満たしておりませんでした。個人事業主としての経験もなかったため、これではお手上げです。事業者さまからは、「1年くらいなんとかなるでしょう」と言われましたが、どうにもならないので、しょうがありません。1年後にきちんと許可を取得できるように、書類の準備や整理について、アドバイスをさせて頂きました。
個人事業主+取締役としての経験が5年以上あったにもかかわらず、許可を取得できなかった事例があります。この会社さまの場合、個人事業主だったころの工事の件数が少なすぎました。請求書+通帳で証明できるのが2年間で数件程度だったのです。他県では、「年間1件の請求書+通帳があれば、経営業務管理責任者の要件を満たす」というところもあるようですが、東京都では、少なくとも3か月に1件ペースの請求書+通帳を求められます。
結局、そこまでたくさんの工事経歴を証明することができず、許可取得を断念する結果となりました。
さて、ここまでは、東京都で建設業許可を取得するために必要なことを記載してきましたが、ここでは、建設業許可を取得したあと、建設業許可を維持するために重要なことについて、記載したいと思います。
経営業務管理責任者がいなくなったら
まず、前提知識として。経営業務管理責任者は、建設業許可の「許可要件」です。「許可要件」である以上、「許可要件」を満たさなくなった場合には、許可を維持することはできません。つまり許可も取得するための要件であり、許可を維持するための要件でもあるのです。このため、「経営業務管理責任者」がいなくなったら、その会社は許可を維持することができません。この場合、いったんは『廃業届』を出して建設業を廃業する必要があります。
「廃業」といっても「建設業をやらなくなる」という意味ではなく「500万円以上の工事をやらなくなる」という意味です。また、いったんは『廃業届』を出して廃業する必要がありますが、新たな経営業務管理責任者が見つかり次第、また新規許可申請をすることは可能です。実際に、経営業務管理責任者が亡くなったり、退職したりして、『廃業届』を提出せざるを得なくなることはよくあります。
「建設業許可の取り下げ」を避けるには?
上記のような『廃業』(=許可の取り下げ)という事態を避けるには、あらかじめ「経営業務管理責任者の候補」を後任として育てておく必要があります。とくに経営業務管理責任者になるには、個人事業主もしくは取締役としての5年の歳月が必要です。逆に、取締役として5年以上登記簿謄本に記載があれば、経営業務管理責任者になりうるのもまた事実です。
建設業界の後継者不足は、深刻な状態です。新規に採用するのも、なかなか難しいと聞きます。しかし、「現在の経管に何か不測の事態が生じた場合(ケガや病気などで業務の遂行が難しくなった場合)」や「高齢により引退せざるを得なくなった場合」など、後任の経営業務管理責任者がいないと、いったんは許可を取り下げなければならなくなります。
廃業といった事態を避けるには、現:経営業務管理責任者が会社に在籍しているうちに、後任の経営業務管理責任者を育成し、5年の取締役期間の経過後に後任に代替わりできるようにしておくのがベストでしょう。
行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可取得の専門家として、いままでいくつもの会社の建設業許可取得に携わってきました。また、経営業務管理責任者の変更届の提出も行っていますし、会社設立時に経管を役員に招き入れるような方法で建設業許可を取得することもできます。
そこで、ここでは行政書士法人スマートサイドがどのようにして経営業務管理責任者の要件調査を行っているのか?簡単にご紹介をさせて頂きます。
経営業務管理責任者の要件調査について
「どんなに建設業許可を取得したい」と願っても、「許可取得のためなら何でもやります」と言っても、経営業務管理責任者の要件を満たさない限り、建設業許可取得は絶対にありえません。弊所では、お客様から建設業許可取得の御相談や、経営業務管理責任者の要件について御相談を受けた際には、下記のようなことを実践して「経営業務管理責任者の要件を満たし、建設業許可を取得できるか否か」を確認させていただいております。
- 登記簿謄本の調査
- 関東地方整備局・都庁建設業課の閲覧コーナーで調査
- 各役所に問い合わせて経歴の確認
- 情報公開制度を利用した開示請求手続き
- 人材紹介会社のお取次ぎ
まずは、「取締役としての経験が5年以上あるか?」登記簿謄本を取得して確認いたします。登記簿謄本の取得は誰にでもできますが、閉鎖事項証明書が必要になったり、過去の会社の所在地の地方法務局に郵便で請求をしなければならないケースがあったりと、意外と面倒なことが多いです。「取締役としての経験が5年以上あると思っていたら、取締役にすらなってなかった」という方も過去にいらっしゃいました。登記簿謄本の裏付確認は、すべての作業に勝る第一優先事項です。
2.関東地整・都庁閲覧コーナーでの情報収集
経営業務管理責任者が過去に他の会社の役員などになっていた場合、その経歴を証明するのに、「関東地方整備局」や「都庁の閲覧コーナー」での閲覧が役に立つ場合があります。都庁の閲覧コーナーでは都知事許可業者の情報、関東地方整備局では国土交通大臣許可業者の情報を閲覧することができます(個人情報保護法の関係で、個人情報に触れることができません)。
これにより、過去の経歴を証明するのに重要な手掛かりが見つかることもあります。また、許可を申請する際に、「経営業務管理責任者証明書」という書類を作成するのですが、その際に記載が必要になる箇所があり、事前に調べておくと便利です。
3.各役所に問い合わせて経歴の確認
過去の経歴を確認するのに必要であれば、他県の建設業課に問い合わせて、許可状況を確認したり、もしくは、国土交通省のホームページ上にある建設業許可業者一覧を検索します。電話での照会に回答してくれるとよいのですが、状況によっては、回答が得られない場合や、そもそもデータとして情報が保管されていない場合もあります。
4.情報公開制度を利用した開示請求手続き
過去に数回、情報公開制度を利用した開示請求手続を行い、過去の資料を入手したうえで、建設業許可を取得した実績があります。情報開示請求には、時間がかかりますが、どうしても方法が無い場合には有効な手段でもあります。例えば、「過去に建設業を行っていたけど、書類をすべて破棄してしまった」とか、「前にいた会社とは疎遠になってしまい、いまさら書類を出してくださいなんてお願いできない」といった時には、行政庁に情報開示請求をすることを検討します。
5.人材紹介会社のお取次ぎ
行政書士法人スマートサイドが、直接御社に、経営業務管理責任者の要件を満たしている人を紹介することはできません。もっとも人材紹介会社の方との間を取り持つことはできます。ご要望に応じて、人材紹介会社のご担当者さまをお取次ぎいたします。なお、必ずお取次ぎできるというわけではありませんので、あらかじめご了承ください。
経営業務管理責任者の要件調査をご希望の人へ
経営業務管理責任者の要件は、「建設業許可を取得する際」「建設業許可を維持する際」の両方にとって、とても重要です。例えば、経営業務管理責任者を常勤の取締役として招き入れ、謄本も変更し、社保加入手続きをとったにも関わらず、いざ申請段階になって「実は、経管の要件を満たしていなかったことが判明した」というようなことがあると、建設業許可取得をできないのはもちろんのこと、謄本の変更や社保加入手続きも無駄になってしまいます。
このような事態を避けるためにも、経営業務管理責任者の要件を満たすか否かは、専門的な知識のもと適確に行う必要があります。
- 経営業務管理責任者を取締役として招聘したい
- 現在の執行役員が経管の要件を満たしているか確認したい
- 複数の取締役のうち、だれが後任としてふさわしいか教えて欲しい
といったご希望がある際には、下記、問い合わせフォームから事前予約制の有料相談をお申込みください。
【6】経営業務管理責任者の要件でお困りなら
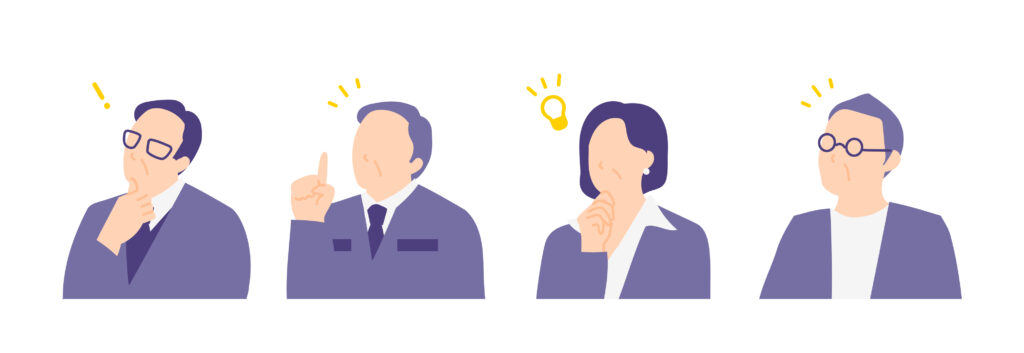
一番初めにも書きましたが、「経営業務管理責任者の理解なくして、建設業許可の取得はありえない」というくらい『経営業務管理責任者』は、とても重要です。『知識不足や、間違った認識で、かえって許可取得が遠のいた』なんてことがないように、十分に、理解を深めたうえで、許可申請にあたってもらいたいものです。
もっとも、面倒な手続きは、すべて専門家にお任せしたいという人もいるでしょう。また、どうしても確実に許可を取得する必要があるため専門家に外注した方が安全であると思う人もいるかと思います。ここまで見てきて分かるように、経営業務管理責任者の要件は、難解な上に、証明資料の準備もしなければならず大変です。そういった際には、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでお問い合わせください。
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応と質の高い面談時間の確保という見地から1時間11,000円の有料相談を実施しています。この有料相談は、御社の状況に則したきめ細やかな分析・提案をさせて頂くとともに、過去の経験や現在の東京都の運用などに鑑みて、本当に建設業許可を取得することができるか否か?を判断させて頂きます。
行政書士法人スマートサイドは、建設業許可申請を専門に扱っている行政書士事務所です。今までたくさんの建設業者さまのお手伝いをしてきました。複雑な案件、手間のかかる案件も柔軟に対応でき、実績も多数あります。不明点や、わからない点などあれば、どうぞ、下記お問合せフォームから事前予約制の有料相談をお申込みください。













